ご先祖は、誰にでもいる。
この一文は、とても当たり前のことのように見えるかもしれません。
でも私たちは、その当たり前を、どれだけ日々の中で感じているでしょうか。
忙しい毎日のなかで、家族のことさえ気にかける余裕がないときもある。ましてや、顔も知らない「ご先祖」のことなど、考えたこともない。そういう人の方が、きっと多いはずです。
けれど、いまこうしてこのお手紙に辿り着いたあなたは、どこかで、うっすらと感じているのではないでしょうか。「ご先祖って、もしかして、ちゃんと関係あるのかもしれない」と。
その感覚は、まだ輪郭のない気づきかもしれません。でも、理由もなく「気になる」という直感は、ときに人生を大きく動かすサインとなるものです。
もしかしたらそれは、あなたの中に流れている「いのちの記憶」が静かに目を覚ましはじめた合図なのかもしれません。
2025年現在、社会は大きな転換点に立っています。
「戸籍制度の見直し」かつてなら考えられなかったような議論が、ごく自然に社会に流れはじめました。
戸籍とは、「血縁を記録するシステム」であり、「家」という単位を国家が認識するための土台でした。
しかし、時代が進むにつれ、その在り方は多くの人の現実とズレを生みはじめています。
同性婚、パートナーシップ制度、選択的夫婦別姓、シングルマザーやシングルファザー、そして血のつながりを超えて結ばれた「家族のかたち」
戸籍という制度の枠組みの外側に、新しい人間関係の形がどんどん生まれてきました。
そんななかで、「戸籍はもういらないのでは?」という声が上がるのも、ある意味で自然な流れです。
けれど私は思うのです。もし戸籍という「制度」がなくなるのだとしたら。
そのときこそ、「つながり」という見えない絆について、私たちは本当の意味で、考え直さなくてはいけないのではないかと。
制度があるからつながっているのではなく、本当は、制度がなくても失われないものがある。
むしろ、制度を超えたところにこそ、私たちの「原点」の存在が浮き彫りになるのではないかと。
それが、「ご先祖とのつながり」です。
名前を知らなくてもいい。記憶がなくてもいい。でも、誰にだってご先祖はいる。
それは、人間としてこの世に生まれてきた以上、絶対に消すことのできない、ルーツの事実です。
今、戸籍制度という「形」が揺れ動いているこの時代だからこそ、「形のないつながり」に、もう一度まなざしを向けてみる。それが、このお手紙の出発点です。
戸籍制度撤廃という現象「ルーツの境界」が曖昧になる時代
戸籍制度が日本に導入されたのは、明治5年。それは、家という単位で人を記録し、国家がその個人を把握・管理するための仕組みでした。
戸主を頂点とした「家制度」と密接に結びついたこの制度は、当時の「国家=家族的共同体」という思想と深く関係しています。以来、150年以上にわたって、戸籍は「ルーツの地図」として日本人の人生と密接に関わってきました。
生まれてから、亡くなるまで。それらすべてが戸籍という紙の上に記録され、「誰と誰がどうつながっているか」を国家が把握してきたのです。
けれど、その「紙のつながり」は、私たちの現実のつながりと、いつしか乖離しはじめました。
たとえば、結婚しても「姓が変わること」への違和感。
実の親と疎遠でも戸籍上は「家族」であることの矛盾。
血のつながらない子どもを育てる養親の苦労。
同性カップルが「他人」として扱われる現実。
多様化する家族の形が、制度の外側にあふれてきたのです。
そして、今。ついに「戸籍制度そのものを見直すべきではないか」という議論が、政治の場やメディアで公然と語られるようになりました。
表向きの理由は「人権の尊重」や「制度の老朽化」です。
たしかにそれも重要な論点です。しかし、より深いところでこの変化は、私たち一人ひとりに問いかけているのです。
「あなたは、どこから来た人ですか?」
「あなたは、自分のはじまりをどう扱いますか?」
なぜなら、戸籍制度が撤廃されるということは、もはや「国家が用意したルーツの地図」に依存できなくなるということ。
それはつまり、自分のルーツとの向き合い方を、「外に任せる」のではなく、「自ら選び取る」時代に入ったということです。
ルーツを語るために、もう血縁や戸籍は必須ではありません。
それでも私たちは、「自分は何者か」という問いを避けては生きられない。
人生の転機、家族の死、子どもの誕生。そのたびに、私たちは「つながり」の正体を問い直さざるを得なくなるのです。
皮肉にも、制度が揺らぐことで、私たちの「つながり」はかえって、「むき出し」になります。
ご先祖とは、戸籍に記された「名前」や「血統」だけの話ではありません。
むしろその逆で、制度が外れたときにこそ、本当の「つながりとは何か?」という問いが浮かび上がるのです。
制度の撤廃は、ただの制度変更ではありません。
それは、「自分と過去との関係性を、誰の言葉でもなく、自分の言葉で語り直す時代」の幕開けなのです。
「ルーツを失うことのリスク」人と組織の軸の喪失
ルーツとは、ただの過去の記録ではありません。それは、選択の軸であり、揺らぎの中で踏みとどまる「心の重力」です。
だからこそ、そのルーツが曖昧になったとき、人も組織も、判断を見失います。なぜなら、「自分がなぜここにいて、どこへ向かうのか」がわからなくなるからです。
個人で言えば、人生の進路や人間関係、働き方や愛し方まで、「選ぶ力」が弱くなる。
そして、選択に迷うだけでなく、選んだあとも「これでよかったのか」と常に揺れ続ける。それはまるで、地図のない航海のようです。
目の前の波に翻弄され、判断はすべて「目先の最適解」に傾いていく。長期視点を持つことが難しくなり、「正しさ」ではなく「正しそうなもの」を追いかけるようになるのです。
この現象は、企業にも同じように表れます。理念を忘れた会社は、迷走します。
創業者の想いや背景が語られなくなった組織では、意思決定がぶれやすくなるのです。
たとえば、ある老舗企業では、「先代のやり方は古い」という言葉とともに改革が進められ、目の前の業績は一時的に上がったものの、次第に社員の結束がゆるみ、離職率が急上昇しました。
理由は単純です。「何のためにやっているのか」が曖昧になったから。どんなに効率がよくても、どんなに合理的でも、「なぜそれをやるのか」が語れなければ、人はついていけない。
企業文化とは、まさに「ルーツの記憶」の蓄積です。
創業当初の想い、乗り越えた危機、培われた信頼。そうした目に見えない記憶が、社員一人ひとりの心の中に「軸」つくっていくのです。それが失われると、組織は不安定になります。
そして、その空白を埋めようとするとき、人は「数字」や「肩書き」や「スローガン」のような、表面的なもので安心しようとします。
でも、それは本当の安定ではありません。「ルーツ」に代わるものなど、本当は存在しないのです。
人も企業も、迷うのは悪いことではありません。揺れる時期があってこそ、成長がある。
けれど、どれだけ揺れても、「戻る場所」があるかどうか。それがあるかないかで、人生の質は大きく変わります。
「なぜこの仕事をしているのか」
「なぜこの人を大切にしたいのか」
「なぜ今、この場所にいるのか」
その「なぜ」を支えてくれるのが、自分のルーツなのです。
だからこそ、ご先祖とのつながりを見つめ直すことは、過去の話をすることではありません。
未来をどう生きるかを決めるための、もっとも深い準備なのです。

戸籍ではなく、記憶でつなぐ「家系との関係性」の再定義
ルーツとのつながりは、戸籍の中にだけあるわけではありません。
名前も知らない、顔も浮かばない、けれど、なぜか心に残っている「家の空気」や「誰かの口ぐせ」。
あるいは、口には出せなかったけれど、ずっと気にしていた親との距離感や、心にひっかかる祖父母の沈黙。
私たちは思っている以上に、無意識のうちに、「ご先祖の記憶」を継いで生きています。
それは、戸籍のような明確な形では表れないけれど、心の中に静かに沈殿している「感情の履歴」のようなもの。
そしてこの「記憶」こそが、私たちとルーツとを、本当につないでいるのです。
ご先祖セラピーでは、こうした「記憶」や「つながり」を丁寧に見つめ直すために、「ジェノグラム(感情家系図)」というツールを用います。
これは、家系図とは異なり、家族一人ひとりの関係性や感情の流れ、出来事などを図式化して可視化していくものです。
たとえば、
・何代にもわたって「母親との距離」が遠い家系
・早くに亡くなる男性が多い家系
・なぜか長男が継がない家系
・誰かが「失踪」することが繰り返される家系 など
こうしたパターンを見つめていくと、「ただの偶然」では済ませられない感情の流れや、代々受け継がれてきた暗黙の誓いのようなものが浮かび上がってきます。
これは決して、「だからあなたの問題はご先祖のせいです」という話ではありません。
ジェノグラムは家族一人ひとりの関係性や感情の流れ、出来事などを図式化して可視化していくものです。「何があったのかを知り、どこで終わらせるかを、自分で選び直す」ためのプロセスです。
ある女性はジェノグラムを描くことで、自分がなぜ「誰かを助けなきゃ」と無理をしてしまうのかを理解しました。
図の中に見えてきたのは、彼女の祖母も、母も、みな「誰かを支え続けて倒れる人生」を送っていたこと。
そして、自分も同じように「誰かの役に立たなければ生きていてはいけない」と、無意識に思い込んでいたことに気づいたのです。
彼女は言いました。「私、家族を支えるために生まれてきたと思ってた。でも、そうじゃない人生を選んでもいいって、ようやく思えたんです」と。これは、戸籍には載らない「心の継承」です。
でも、たしかに引き継がれ、そして今、書き換えられていくものです。
ご先祖とのつながりは、「血」や「名前」ではなく、「気づき」と「祈り」によって更新されていきます。
どんな家にも、言葉にされなかった感情がある。
叶えられなかった願いがある。
誰かを想う気持ちが、届かなかった時間がある。
その未完の記憶を、今ここに生きる私たちが静かに受け取り、癒し直し、つなぎ直していく。
それが「原点との再接続」であり、新しい時代の「家との関係性」の形なのです。
なぜ今、「原点」が必要なのか?個人の人生戦略との関係
情報があふれ、選択肢が増え、価値観もライフスタイルも多様になった現代。
私たちは「何を選んでもいい」時代に生きているはずなのに、なぜか「何を選んでいいかわからない」と迷い続けてしまう。
それはなぜでしょうか。理由のひとつは、「自分の原点」を知らないまま、人生の選択を迫られるからです。
原点とは、「自分が何を信じ、何に根ざしているか」という問いに対する答えです。
それは親からの影響かもしれないし、ご先祖の生き様かもしれない。あるいは、自分の中でずっと言葉にならなかった「大切なこと」かもしれません。
いずれにしても、原点は「選択の基準」になります。
・やりたい仕事が複数あるとき、どれを選ぶか
・この人と一緒に生きていくかどうかを決めるとき
・苦しみの中で「踏ん張るか、引くか」を選ぶとき
その判断に軸を与えてくれるのが、自分の原点です。それが曖昧だと、私たちは「他人の正解」にすがりやすくなります。
SNSの発信、時流のトレンド、成功者の言葉。それらに飲まれやすくなるのは、自分の「原点」が定まっていないからです。
だからこそ、「私はどこから来て、どこへ向かいたいのか」という問いは、どんな時代であっても、私たちに必要なのです。
私たちは今、BANIの時代を生きています。
Brittle「脆くて壊れやすい」Anxious「漠然とした不安に満ちている」
Nonlinear「すべてが予測不能で直線的に進まない」
Incomprehensible「理解不能なことが次々と起こる」
「何が正解か」「これを選んでいいのか」その問いに答えが出ない不安定な世界で、私たちは立ち尽くしています。そんな時代だからこそ、必要なのは「原点」です。
情報や他人の意見に流されず、目の前の混乱に飲み込まれずにいられるのは、「自分は何者か」「どこから来たのか」を知っている人です。
原点を知ることは、単なる過去の記録を振り返ることではありません。
それは、迷ったとき、立ち止まったときに立ち返る「自分だけの座標軸」を持つことです。
BANI時代では、正解を外に求めるのではなく、「自分が何を大切にするか」を深いところで握りしめる力が、何より大切になります。
たとえば、誰かの期待に応えるために動き続ける人は、その期待が崩れた瞬間に、自分の存在意義も見失ってしまうでしょう。
目の前の結果や他人の評価に頼る人ほど、状況が変わるたびに軸を見失い、不安に飲み込まれていきます。
でも、自分の原点を持っている人は違います。
「なぜ私はこれを選ぶのか」
「何のためにこの道を進むのか」
その問いに、自分なりの言葉で答えられる人は、外側の不安定さに揺さぶられながらも、倒れずに立ち続けられるのです。
その原点を見つける手がかりは、意外と身近なところにあります。
それが、ルーツです。
「うちの家系はなぜこうなのか」
「母がよく言っていたあの言葉」
「なぜ自分はこの感情を繰り返してしまうのか」
そんな小さな疑問に耳を澄ませるとき、そこには必ず「自分が背負ってきた物語」があります。
そして、その物語の中には、自分を支える価値観の種や、何世代にもわたる願いの欠片が眠っているのです。
BANI時代に求められているのは、「これが正解」という答えを持つことではありません。
むしろ、答えがなくても進める力を持つことです。自分の原点を知っている人は、答えが出ない問いに出会ったときも、「それでも、これを選びたい」という意志を持てる。
その力が、不安定な時代を生き抜くための、何よりの武器になるのです。
だからこそ、今、
「わたしはどこから来たのか」
「私は何を引き継ぎ、何を終わらせたいのか」
「私は誰の祈りの上に生きているのか」
その問いを、ゆっくりと、静かに、抱きしめてみてほしいのです。
それがきっと、BANI時代をしなやかに生き抜くための、あなたの「原点」になります。

「祈りは見えない資産」精神資本としてのつながり
現代は、目に見える資本に偏りすぎた時代です。
お金、肩書き、フォロワー数、学歴、スキル。数値化できるものはすぐに価値と認識され、そうでないものは、後回しにされがちです。
けれど、人間の深い安心感や創造性を支えているのは、必ずしも「見える資産」ではありません。
むしろ、多くの場合、それは「見えないつながり」によって育まれています。その代表的なものが、「祈り」です。
祈りというと、宗教的な響きが強くなるかもしれません。けれど、ここで言う祈りは、もっと生活に近いものです。たとえば、
・小さな頃、出かけるあなたの背中に手を当ててくれた母の気配
・受験の日、静かにお守りを渡してくれた祖父母のまなざし
・顔も知らない曽祖母が、毎日家族のために唱えていたお経の声
そういった、名もなき「祈りの連なり」が、私たちの背後には、静かに積み重なっているのです。
それは、紙に記されることも、ニュースになることもありません。
けれど、その「祈られていた」という感覚は、確かに人の心を深く支える「見えない資産」になります。
現代心理学やトラウマ研究でも、「安心感」は人間の創造性、行動力、愛着の質を高める鍵だといわれています。しかし安心感は、外側から与えることはできません。
根源的な安心感は、「自分はこの世界に歓迎されていた」という記憶によって生まれます。
この記憶は、必ずしも「はっきりした体験」として残っていなくても構いません。
むしろ、「自分は見守られていた気がする」という曖昧な感覚こそが、深い部分での土台になっていることが多いのです。
そして、その見守りの起点が、「祈り」という形で代々流れてきたとしたら。それは、血よりも深い絆であり、制度よりも強い支えになり得るのです。
ご先祖セラピーでは、「祈りの連なり」を思い出し、もう一度感じ直すことを大切にしています。
自分の命が、たくさんの「願い」の上にあったことを知ると、人は自然と、自分を大切にしたくなります。
それまで「頑張らなきゃ」「結果を出さなきゃ」と焦っていた人が、「生きてるだけで、もう受け取ってたんだな」と、ふっと力が抜けていく。
この「無条件の受容感」は、現代社会のどこを探しても手に入りにくいものです。
でもそれは、ルーツをたどり、祈りを見つけ、その存在にただ「気づく」ことで、少しずつ心に降りてきます。
資産とは、本来「未来の可能性を広げるもの」です。
そう考えるとき、「祈り」や「つながり」もまた、十分に「精神的資本」と言えるはずです。
そして、制度や数字がどれほど変わっても、この「祈られてきた記憶」は、誰にも奪うことはできません。
祈りは、目には見えなくても、あなたの中に流れています。
思い出せば思い出すほど、それは力になり、
人生を動かす静かなエネルギーとなって、
あなたの選択や言葉やまなざしに、にじみ出ていくのです。
血ではなく、物語でつなぐ時代へ
「血のつながり」に、どれほどの意味があるのか。この問いが、かつてないほど現実的になってきました。
家族の定義は変わりつつあります。血縁をもたない親子、同性カップル、ステップファミリー。そこに流れているのは、血ではなく、「物語」です。
誰と、どんな関係を築いてきたか。どんな時間を共に過ごし、どんな感情を共有してきたか。
その積み重ねが「家族」を形づくるようになってきています。
そしてこの流れは、ご先祖との関係にも、静かに「波紋」を広げはじめています。
たとえば、自分を育ててくれたのは、実の親ではなく養親だった。
戸籍上の祖父は他界していたが、近所のおじいさんが人生の節目にいつも助けてくれた。
血はつながっていなくても、「大切な存在」だった人。
あるいは、ある種の「憧れ」や「共鳴」を感じている歴史上の人物、著名人や偉人、恩師、あるいは書物を通して出会った誰か。
そういった存在を、自分の「ルーツの物語」に組み入れていく人が、今、少しずつ増えてきています。
ルーツとは、「血の記録」であると同時に、「生き方の系譜」でもあるのです。
ここでご先祖セラピーが大切にしている視点があります。
それは、「血の重さ」を引き受けつつ、そこに「物語の自由」を与えることです。
毒親との関係に苦しんできた人にとって、「親を大事にしなさい」「先祖を敬いなさい」という言葉は、重荷でしかないことがあります。
でもそのとき、「血はつながっているけれど、心はつながれなかった」ことを悲しんでもいい。そのうえで、「わたしは誰と心をつなぎたいのか」を選び直していい。
そう許されたとき、「血のルール」から自由になり、「物語の編集権」を取り戻せるのです。
ご先祖との関係もまた、「敬う」ことだけが正解ではありません。
「わたしの中には、ご先祖から受け継いだ強さがある」
「でも同時に、断ち切りたい記憶もある」
その両方を抱きしめながら、自分の物語を更新していく。これこそが、「血」に縛られない、新しい「物語」の形だと、私は思います。
物語は、血よりも自由です。だからこそ、癒しと希望の力を持ちます。
私たちがどんな家に生まれ、どんな親に育てられたか。それは変えられない事実かもしれません。
でも、そこからどんな物語を紡ぎ直すかは、いま、ここから選ぶことができる。
家系の記憶も、ご先祖の祈りも、自分の言葉で語り直した瞬間から、「わたしの物語」として再構築されていきます。
そしてその物語は、誰かの人生にとっての「祈り」となり、新しい「つながり」を生み出す土壌になっていく。
血を超えて、言葉がつなぐ。制度を超えて、物語が受け継がれていく。
それがこれからの、「ご先祖との関係性」のあり方なのかもしれません。
「ルーツの解像度」が、人生の質を変える
ルーツとは、記録でも、血筋でも、歴史でもあるけれど、もっと本質的には、「自分を支える深層の物語」です。それがある人は、人生の選択に確信を持ちやすくなります。
ブレても戻る場所があり、迷っても「なぜこの道を歩きたいのか」が、ちゃんと語れる。
逆に、その解像度が低いままでは、どんなに自由な時代でも、どこか心許ないまま生きることになります。
情報はあっても信じきれない。選択肢はあっても選びきれない。人と関わっても、どこかで「自分が誰か」が曖昧なまま。その違いは、ルーツの「解像度」の差なのです。
ご先祖セラピーでは、「記憶をたどること」や「祈りの連なりに気づくこと」、「ジェノグラムで見える化すること」などを通して、その解像度を少しずつ上げていくことを目指しています。
名前を知らない祖先に、心の中で「ありがとう」と言ってみる。
昔のアルバムを開いて、語られなかった物語に想像を巡らせてみる。
親との関係で感じていた「言えなかった気持ち」を、ようやく自分の言葉で見つめ直してみる。
それだけで、心の中にひとつ「地図」が生まれます。
誰から何を受け取り、何を終わらせ、何を引き継いでいくのか。その地図があるかないかで、人生の質はまるで変わっていくのです。
「自分が何者かわからない」と感じている人にこそ、ルーツに触れてほしい理由があります。
それは、「自分を変える」ためではなく、「すでに在るもの」を思い出すため。
私たちは、ゼロから人生を築いているわけではありません。何代もの命のバトンを経て、ようやくここにいる。
その背景を思い出したとき、「もっと自分らしく生きなければ」ではなく、「すでに、ちゃんとつながっていたんだ」と感じられるようになる。
そこから生まれる選択は、力みによるものではなく、静かな確信とともに、自然と踏み出せるものです。
今、世の中は急速に変化しています。家族のかたちも、働き方も、生き方も揺れ動いています。
戸籍制度の見直しが現実味を帯びる中で、「制度」ではなく「心のつながり」こそが私たちの土台になっていく時代に入ったといえるでしょう。
「誰にでも、ご先祖はいる」この普遍的な真実が、かつてないほど問い直されている今。
私たち一人ひとりが、自分の原点ともう一度向き合い、「ルーツの解像度」を上げていくことは、社会全体にとっても大きな意味を持つのだと思います。
自分の軸を取り戻すこと。
家族の物語を癒し直すこと。
未来を選びなおす勇気を持つこと。
それは決して、特別な人だけが行う「スピリチュアルな儀式」ではありません。
私たちは日々、たくさんの情報や選択にさらされながら、「今を生きる」ことに精一杯でいます。
でもふとした瞬間、理由もなく誰かのことを思い出したり、昔の写真を見て涙が出てきたり、お墓の前で静かに手を合わせたくなったり。
そんなとき、そこには言葉にならない「つながり」が流れているのだと思います。
このお手紙を書きながら、改めて感じたことがあります。それは、ご先祖とは「過去にいた人たち」ではなく、「いまの自分を生きること」の背景に、確かに存在しているということ。
戸籍制度の変化は、表面上は制度の話かもしれません。
でもその奥には、「わたしは誰か?」という根源的な問いが静かに揺れているのです。
誰だって、ご先祖はいる。たとえ記録がなくても、思い出せなくても、私たちは、祈られ、願われ、生まれてきた。この命の中には、語られなかった物語が宿っています。
だからこそ、いまここから、自分自身の「ルーツとの関係性」を問い直すことができたなら…人生は少しずつ、静かにほどけていきます。
未来の選択に迷ったとき、心がふらついたとき、立ち戻れる「原点」を持っている人は、強い。
祈られていたことに気づいた人は、優しくなれる。
ルーツの物語は、過去の話ではありません。これからの未来を、どんなふうに生きていくか。その「意志のよりどころ」として、いつでもそばにあるものだと思います。
このお手紙を読み終えたあなたの中にも、きっともう、その物語は静かに息づいているはずです。

編集後記
BANI時代は壊れやすく、不安で、予測不能で、理解しがたい時代。
そして今、戸籍制度撤廃という大きな転換点が訪れています。
血縁や制度に縛られない家族の形が広がる一方で、私たちは「自分はどこから来たのか」「誰の願いを受け取って生きているのか」という問いに向き合わざるを得なくなっています。
名前を知らなくても、記憶がなくても、
いま自分がここにいるという事実が、その証です。
「自分は何者か」を知るためには、ルーツの記憶に触れ、受け取ったものを知り、
引き継ぎたくないものはそっと手放していくことが必要です。
戸籍制度がなくなる時代は、「何を大切にして生きていくのか」を自分で選び直す時代でもあります。
それは不安定な時代をしなやかに生き抜く力となり、誰かの祈りに応えるように、未来への新しい物語を紡ぐ力になるのだと思います。
また、つぎのお手紙でお会いしましょう。
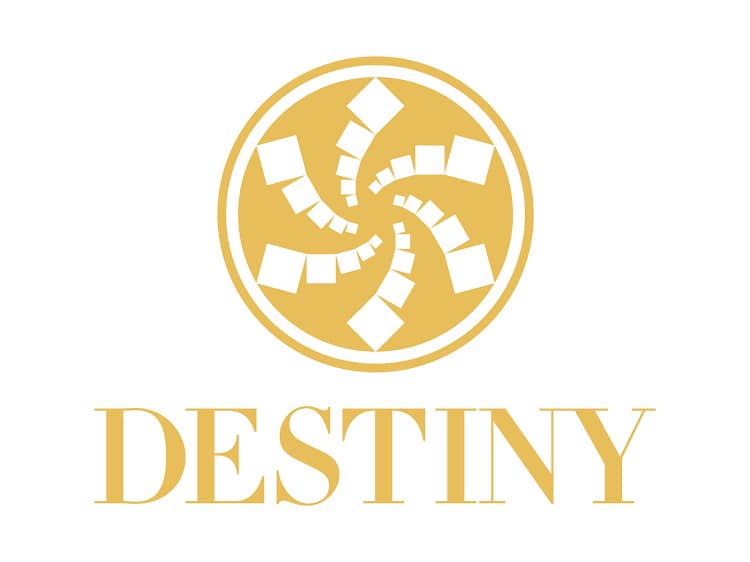
あなたとあなたの大切な人の人生が愛で満ち溢れるものであり続けますようにとの願いを込めてDESTINYからのお手紙をお届けさせていただいています。
「このテーマについて知りたい」
「こんなサービスがあったらいいな」
「今、こんなことで悩んでいます」
あなたの声をぜひ聴かせていただけませんか?
あなたの声をぜひ聴かせていただけませんか?
https://docs.google.com/forms/d/1cmI3soV5IdmhqFvLVkQw0pNYEtJqS07syR2NuVXk0xk/edit