「だれかに愛されたとき、はじめてそのねこは死んだ。」
──佐野洋子『100万回生きたねこ』より
何度も生きて、何度も死んで、与えることに誇りを持って生きてきた一匹のねこ。
それが、はじめて「愛される」という体験をしたとき、彼は初めて、自分の「命」を手放すことができた。
この物語の一節は、「受け取ること」が、どれほど深く、そして人生を変える行為なのかを教えてくれます。
ビジネスや人間関係の中で、「与えること」は評価されやすく、「受け取ること」は軽視されがちです。
しかし、報酬、信頼、感謝、愛情...。本当の意味でそれらを受け取れないと、人生はうまく循環しません。
このお手紙では、
「なぜ人は受け取ることが苦手なのか」
「それが人生とビジネスにどう影響するのか」
「どうすれば受け取る力を取り戻せるのか」
というテーマを、心理・文化・家系・実践の観点から丁寧に解きほぐしていきます。
「私は、受け取っていいのだろうか?」
もしあなたがそう感じたことがあるなら、このお手紙はあなた自身への静かな「許可」になるかもしれません。
なぜ「受け取ること」が難しいのか
「ありがとう」
「助かったよ」
「君にお願いしてよかった」
こういった言葉を、あなたはどれくらい素直に「受け取れて」いるでしょうか。社会人として、あるいは人との関係の中で、「与える」「尽くす」「努力する」ことは、多くの方が自然にできることかもしれません。
むしろ、それができる人ほど、信頼され、必要とされやすい側面もあるでしょう。しかしその一方で、「受け取る」ことに、どこか苦手意識や抵抗感を持つ方も少なくありません。
ここで言う「受け取る」とは、単に物やお金をもらうという意味ではありません。
「感謝」「評価」「信頼」「報酬」「愛情」など目に見えないものも含めて、他者から向けられたエネルギーを、自分の中に許可して取り込む行為を指します。
この「受け取り力」が低いと、次のような傾向があらわれやすくなります。
・褒められても「そんなことない」と否定してしまう
・好意を受け取ると申し訳なくなる
・頼ることに強い抵抗感がある
・報酬を受け取る際に遠慮が生まれる
・「与える側」にばかり立とうとしてしまう
一見、「美徳」のように見えるこれらの傾向は、実は自己価値感や、過去に身についた思考パターンに起因している場合が多いのです。
「受け取り下手」は、自分を守るための反応でもある
人は「与える側」に立つことで、ある種の安心を得られます。
自分の意思で行動している感覚、相手を助けているという感覚は、自尊心を保ちやすく、コントロールを持っているという認識にもつながります。
しかし、「受け取る」ことはどうでしょうか。それは、相手のまなざしや思いを受け入れるということであり、自分の価値そのものを認める必要がある行為です。
そこには、「無防備さ(vulnerability)」が求められます。
自分のままで「価値がある」「必要とされている」と信じる勇気が、必要になるのです。
受け取れないという反応は、ある意味では、傷つかないようにするための「自己防衛」でもあります。
日本文化にある「遠慮」と「謙遜」の影響
この「受け取りにくさ」は、個人の性格だけでなく、日本社会全体に根づく文化的な背景とも関係しています。たとえば
・謙虚であることが美徳とされる
・褒められたときに「そんなことないです」と返すのが礼儀
・自己主張よりも“空気を読む”ことが評価される
こういった文化的背景の中で育つと、無意識に「受け取ること=図々しい」「主張すること=わがまま」という感覚が染み込んでしまいます。
結果として、「ありがとう」と言われるだけで申し訳なくなったり、誰かの親切に対して「お返ししなきゃ」とすぐに思ってしまうなど、受け取りの回路が閉じてしまうのです。
まずは「受け取れなかった自分」を責めないことから
「どうして私は素直に受け取れないのだろう」
そう悩む方に、まず伝えたいことがあります。それは、受け取れないのは「あなたの弱さ」ではないということです。それは、長い年月をかけて身につけた生きるための知恵であり、あなたが生きてきた文化や環境の中で形成された自然な反応でもあります。
だからこそ、まずは「なぜそれが難しかったのか」を、あたたかく見つめ直すことがとても大切なのです。
「受け取れない自分を責める」のではなく、「そうせざるを得なかった理由がちゃんとあった」と理解してあげること。それが、受け取る力を取り戻す最初の扉になります。

受け取る力は「自己価値の感覚」から始まる
「受け取ることができない」という感覚の背景には、自己価値の認識が深く関わっています。言い換えれば、「自分には、それを受け取るにふさわしい価値がある」と、心の奥で信じられているかどうかが、受け取る力の鍵になります。ここでいう「自己価値」とは、何かを成し遂げたから、役に立ったから、という条件付きの評価ではなく、「存在していることそのもの」に対する根本的な価値の感覚です。
しかし現代では、この自己価値が「成果」や「他人からの評価」によって左右されやすくなっています。
「もっとがんばらなきゃ、認められない」
「人の役に立っていないと、私は無価値だ」
そんな思い込みを持ちながら生きている人も少なくありません。その結果、好意や信頼、報酬が差し出されたとき、こんなふうに思ってしまうのです。
「こんな自分が受け取っていいはずがない」
自己肯定感と自己価値感は違います
よく混同されがちなのが、「自己肯定感」と「自己価値感」です。
自己肯定感とは、「自分には良い部分もある」と思えること。たとえば、「努力できる自分」「人に優しくできる自分」などを肯定する感覚です。一方で、自己価値感はもっと静かで深いものです。
「なにもしなくても、ここに存在しているだけで私は価値がある」
と感じられる感覚。それが自己価値感です。この感覚が育っていないと、どれだけ努力しても、成功しても、人に感謝されても、そのエネルギーを自分の中に通す通路が開かれないままになってしまいます。
受け取れない人に多い3つの思考パターン
受け取れない人には、いくつかの共通する思考のクセがあります。
1. 責任感が強すぎる
「自分が頑張らなければ」「迷惑をかけたくない」という思いが強すぎて、受け取ること=他人に負担をかけると感じてしまう。
2. 他人との比較がやめられない
「自分より頑張っている人がいる」「私はまだまだ」と感じてしまい、受け取る資格がないと無意識に判断してしまう。
3. 成果が出ていないと自分を許せない
「まだ結果が出ていないから、もらうのはおこがましい」と、過程の自分には価値がないと感じてしまう。これらは誠実でがんばり屋な人ほど抱えやすいものです。しかし、それが過剰になると、「自分には受け取る価値がない」と感じる思考回路ができあがってしまいます。
「受け取ってもいい」自分への許可がすべての始まり
受け取る力を育てるために必要なのは、「私は受け取っていい」と、自分に許可を出すことです。
たとえば、
・褒められたら、笑顔で「ありがとう」と言ってみる
・ごちそうになったときに「ごめんね」ではなく「うれしい」と返してみる
・欲しいと思ったものに「それを望んでもいい」と認めてみる
こうした小さな行動の積み重ねが、あなたの内側にある「受け取る器」を少しずつ育ててくれるのです。「受け取る価値があるかどうか」は、他人が決めることではありません。自分で、自分に許可を出せるかどうか。それが全てなのです。

家系・先祖・無意識の記憶と受け取りブロック
「なぜか分からないけれど、受け取ることに罪悪感がある」
「好意や報酬を受け取ると、どこかで自分を責めてしまう」
このような感覚には、個人の性格や経験だけでは説明しきれない「深層の背景」がある場合があります。それが、「家系的な感情の継承」や「先祖から受け継がれた無意識の記憶」です。
私たちは、「見えない記憶」を受け継いでいる
多くの人が、自分の育った家庭環境や親の言動が、自分の価値観や感情に影響していることを何となく感じています。しかしその背景には、親や祖父母、さらにその先の世代から受け継がれた、「無意識の思い込み」や「行動パターン」が存在していることがあります。
たとえば、次のような家系的な価値観に心当たりはないでしょうか?
・「自分より他人を優先しなさい」
・「お金の話をするのは、はしたない」
・「欲を出すとバチが当たる」
・「がまんできる人が立派」
これらは一見、謙虚で美しい考え方にも見えます。しかし、度を越して根付いてしまうと「受け取ること=いけないこと」という無意識のブロックになってしまうのです。
代々続く「遠慮と犠牲」のパターン
家系によっては、代々「与えること」「耐えること」「遠慮すること」を、美徳として受け継いでいることがあります。
たとえば、
・戦中・戦後の苦しい時代に育ち、「欲しがらなければ守れる」と信じていた祖母
・経済的に厳しく、常に節約と我慢で家庭を支えた両親
・自分の欲や夢を後回しにして、家族や仕事に尽くしてきた姿
こうした記憶や行動は、言葉では語られなくても、態度・空気・感情のニュアンスとして次世代に受け継がれていきます。そしてそれが、「自分は受け取るにふさわしくない」という根深い思い込みをつくってしまうのです。
家系の「感情の風景」は、知らずに染み込んでいる
私たちは、日々の中でたくさんの「見えない情報」を受け取っています。親の表情、空気感、言葉にされなかった思い。それらは、無意識のうちに「正しさ」として体の中に染み込んでいます。
たとえば、「お母さんが疲れているのに、自分が何かを欲しがったら悪い気がする」という感覚を、小さな頃に感じた人は少なくありません。その積み重ねが、「欲を出すと人に迷惑がかかる」「助けを求めるのはわがままだ」といったブロックとなって残ってしまうのです。
これは「感情の遺伝」とも言える現象です。目に見える遺伝子とは別に、「無意識の記憶」や「感情のクセ」が受け継がれているということです。
「先祖からのメッセージ」は変化している
興味深いことに、先祖たち自身も「あなたにはもっと豊かになってほしい」と願っていることがあります。
かつての世代は、生きることそのものが試練でした。
だからこそ、節約・我慢・自己犠牲が必要だったのです。しかし、時代が変わり、今を生きる私たちには「別の役割」が与えられています。それは、「受け取ることを学ぶ役目」です。
遠慮や我慢のバトンは、もう十分につながれてきました。だからこそ今、自分が豊かになること、感謝や信頼、報酬を素直に受け取ることを、「家系全体の癒し」として実践する時期がきているのです。
あなたが受け取ることで、癒される人がいる
もしあなたが今、「自分なんかがもらっていいのかな」「そんなに価値があるように思えない」と感じていたとしても、それはあなた自身の声であると同時に、ご先祖や家族の誰かがずっと抱えてきた痛みの声でもあるかもしれません。
だからこそ、その思いを超えて「受け取っていい」「もう我慢しなくていい」と自分に許すことは、「過去の誰か」をも救う行為でもあるのです。
受け取ることは、単なる行為ではなく「生まれた家系・無意識の記憶と向き合う」深いプロセスです。
それに気づいたあなたは、すでに新しい扉の前に立っています。
「仕事は与えるもの」「相手に価値を届けることがすべて」そう信じて頑張ってきた方は多いのではないでしょうか。
たしかに、ビジネスの本質は「価値を提供すること」にあります。
しかし、もうひとつ見落とされがちな大切な本質があります。
それが、「受け取ること」もまた、ビジネスの一部であるということです。
ビジネスは「交換」で成り立っています
ビジネスは一方通行ではありません。提供する側と、受け取る側のあいだで「価値とエネルギーが循環すること」で成り立っています。「お金」はその循環のシンボルです。
「商品やサービスを提供する代わりに、対価としてお金を受け取る」これはただの取引ではなく、信頼と評価がかたちになったものでもあります。
...にもかかわらず、次のような悩みを抱える人は少なくありません。
・自分の商品やサービスに価格をつけるのが苦手
・相手のために尽くしすぎてしまい、疲弊してしまう
・「これくらいでお金をもらっていいのか」と感じてしまう
・無料で提供しすぎて、自分が空っぽになる
これらの背景にあるのが、まさに「受け取ることへのためらい」です。
価格=自己価値の表現である
特にフリーランスや個人事業主、クリエイターや講師など、「自分の知識・時間・才能」を商品として提供する人ほど、価格設定や報酬の受け取りに葛藤を抱えやすい傾向があります。
「この金額で提供するなんて、おこがましいかもしれない」
「クライアントの負担にならないよう、安くしたほうがいいかも」
そうした「思いやり」や「配慮」が、結果的に自己価値の低下を招いてしまうことがあります。
ここで大切なのは、価格とは「自分を評価する行為」ではなく、「相手との信頼関係をつくるための設計」だということです。
相手があなたのサービスに価値を感じ、対価を支払ってでも受け取りたいと感じてくれること。その循環があってはじめて、ビジネスは継続的に回っていきます。
受け取らないと「信頼」も循環しません
「無償で提供し続ける」「恩返しは要らない」「報酬はあとでいい」これらのスタンスは、一見かっこよく見えることがあります。しかし、これを長く続けていると、相手は「受け取るタイミングを見失う」ようになっていきます。
「なにも受け取ってくれない人」には、やがて「信頼」や「投資」を返しづらくなってしまうのです。本当の意味で人に影響を与える人は、自分の器を開いて「ありがとう」と「いただきます」を受け取る人です。
報酬、感謝、フィードバック、応援...。これらすべてを受け取ることで、はじめて関係性の「循環」が生まれます。
「お金=評価」ではない。「お金=共鳴のしるし」
ビジネスにおいて「お金を受け取る」という行為には、まだまだネガティブなイメージを抱く人が多くいます。
・お金の話をすると信頼が下がるのでは
・商売っ気を出すと「本物のスピリチュアル」じゃない
・自分のために稼ぐなんて、利己的だ
でも、本来お金とは「共鳴のしるし」です。あなたが提供したものに対して、相手が「受け取りたい」と感じた。その感情を、かたちにして渡してくれるのがお金です。だからこそ、お金を受け取ることは、自分の価値を認め、相手の共鳴を信頼する行為でもあります。
受け取ることは、「自分を信じる」ことでもある
価格を提示すること。
感謝の言葉を受け取ること。
好意を素直に受け取ること。
これらはすべて、「自分が受け取るに足る存在である」と信じているからこそできる行動です。ビジネスにおいても、プライベートにおいても、この受け取る力が育っていくほど、信頼・評価・報酬・応援が自然と循環しはじめます。
評価・報酬・応援が自然と循環しはじめます。

感受性と豊かさの「受け取り設計」
「なんとなく、心が重たくなる」
「周囲の空気に飲まれて疲れてしまう」
「人の期待や感情が、自分のもののように感じられてしまう」
このような感覚に心当たりのある方は、感受性が高い人である可能性が高いです。感受性とは、「感じる力」であり、「受け取る力」でもあります。一見すると、豊かさを受け取るための大きな強みのように思えますが、実際には「受け取りすぎて、流せなくなる」という課題も抱えています。
感受性が高い人ほど、受け取りすぎてしまう
感受性が強い方は、まわりの感情や空気を繊細にキャッチできます。場の雰囲気の変化や、言葉にされない感情にも敏感です。それ自体は素晴らしい資質なのですが、問題なのは「その情報を自分の中にためこんでしまう」という傾向にあります。
誰かの悲しみを、自分のことのように背負ってしまう。期待に応えなければというプレッシャーを、過剰に感じてしまう。感謝や賞賛を受け取ったときにも、「本当にそれをもらっていいのか」と迷ってしまう。
このように、受け取った感情やエネルギーを“循環”させるのではなく、自分の内側に留めてしまうため、心身が疲弊しやすくなるのです。
豊かさは「流れる」ことで育っていく
ここで大切なのが、「流れを設計する」という視点です。水が滞るとよどみます。エネルギーも同じで、「与える」「受け取る」「流す」がバランスよく回ってこそ、豊かさの循環が生まれます。
感受性が高い人は、「与える」ことに慣れています。「受け取る」ことにも敏感です。
でも、最後の「流す」つまり、「受け取ったものを自分の中でちゃんと咀嚼し、次に渡していく」というプロセスが苦手なことが多いのです。
受け取るためには「設計」と「選択」が必要です
感受性の高い人にとって、豊かさを受け取るには、ある程度の「設計」が必要です。
たとえば
・どんな言葉を受け取りたいか、あらかじめ明確にしておく
→ 誰からのフィードバックを受け取るか、自分に必要な言葉を選ぶ
・日々の情報の流れを「フィルター」にかける習慣を持つ
→ SNSや人間関係のノイズを整理する
・「これを受け取りたい」と心から思える環境・人と関わる
→ 無理して付き合う関係は、受け取る器を曇らせてしまう
このように、「受け取る力」を自然に発揮できる環境づくりや関係性の選択が、非常に重要になります。
自分に合った「受け取り方」を知る
さらに言えば、「受け取り方」も人それぞれです。ある人は「言葉をかけてもらうこと」でエネルギーが回復します。またある人は、「静かな空間で、ひとりで感情を味わうこと」で豊かさを感じます。また別の人は、大切な人と時間を共有することで「受け取った」と感じます。
自分にとって「受け取る」とは、どんな体験なのか。それを知っておくことで、豊かさの回路がスムーズに開いていきます。
感受性は、「豊かさの器」でもある
繊細さや感受性を持つことは、ときに生きづらさの原因になることがあります。でもそれは、言い換えれば人の思いや美しさ、愛情や感謝を深く受け取ることができる「豊かさの器」を持っているということです。だからこそ、その器に合ったかたちで、丁寧に「受け取りの設計」をしていくことが大切です。
そして、自分にとって心地よい循環のスピードと量を知ることで、感受性は「疲れやすい弱点」ではなく、「共鳴力の強さ」へと変化していきます。

受け取る力を育てる実践ステップ
「受け取る力を育てたい」そう思っても、いざ日常に戻ると、つい遠慮してしまったり、自己否定が顔を出したり、なかなか変化を実感できないことも多いです。ここでは、日々の生活の中で「受け取る力」を丁寧に育てていくための実践的なステップをご紹介します。
特別な準備は不要です。むしろ、ささやかな行動の中に「受け取る力の回路を開く鍵」があるということに気づいていただけたらと思います。
Step1「ありがとう」を、ちゃんと受け取る
最初のステップは、誰かからの「ありがとう」を、逃げずに受け取ることです。
「いえいえ、そんな…」「いや、たいしたことしてないので」と、謙遜で流してしまう方は多いですが、ここをあえて止めてみましょう。おすすめの受け取り方は、「そう言ってもらえて、うれしいです」と返すことです。ポイントは、「私なんて」と否定するのではなく、「それを言ってくれたあなたの気持ち」をちゃんと受け取るという姿勢です。こうした小さなやりとりが、「受け取る力」を日々磨いてくれます。
Step2「小さな欲」をゆるしてみる
受け取る力が弱っているとき、自分の「欲すらも許せなくなっていることがあります。
・おやつが食べたいけどがまんする
・欲しかった服を見つけたけど「いまは無駄」と諦める
・誰かに会いたくても「迷惑かも」と遠慮する
こういった小さな欲を、「大事にしていい」と許すことは、「私は受け取ってもいい存在なんだ」と自分に伝える行為でもあります。今日ひとつ、「これはわがままではなく、感受性の声だ」と思って叶えてあげることを、ぜひやってみてください。
Step3「与えすぎた記憶」と向き合い、整える
人によっては、これまでに「与えすぎてしまった体験」が、受け取ることへのブロックになっている場合があります。
・無償で人に尽くして、疲れてしまった
・誰にも助けを求めず、一人で抱え込んできた
・「ありがとう」も言われないまま、与え続けてきた
これらの体験を「なかったこと」にせず、一度、心の中で見つめ直す時間を持ってみてください。「よくがんばってきたね」「当時の自分に、ありがとうって言いたい」そんなふうに、自分自身の「過去の頑張り」をねぎらうことは、新しい「受け取り力の回路」を開く助けになります。
Step4目に見えないものを「信じて受け取る」
最後のステップは少し抽象的ですが、私たちDESTINYがとても大切にしていることです。それは、目に見えない豊かさを「受け取る」と意図することです。
たとえば
・誰かがくれた「見守る気持ち」
・自然の中にある「静かな癒し」
・ご先祖や家族の「あなたに豊かになってほしい」という想い
こういったものは、物理的には見えませんが、確かに存在し、私たちの中に流れこんでくるものです。「私は、いま、それを受け取っていい」と自分に許可を出すだけで、受け取りの感覚は確実に変わっていきます。
「受け取ること」は、日常の選択から始まる
受け取るという行為は、特別な能力でも、突然できるものでもありません。それは、日常の中で何を感じ取り、どう応じるかという「選択の積み重ね」です。
・自分に優しくする
・褒め言葉を否定せずに受け取る
・必要なときは「助けて」と言う
・好きなものを、堂々と選ぶ
こうしたささいな行動のなかにこそ、本当の「受け取る力」は息づいています。

豊かさとは、受け取りながら生きること
「与えること」は、美徳です。それは疑いようのない真実でしょう。けれど同時に「受け取ること」もまた、美しさであり、信頼であり、愛のかたちのひとつなのです。
「与え、与え、与える」それだけでは、どこかで自分が空っぽになってしまいます。人は、自分が満たされたぶんだけ、やさしくなれます。受け取ったものの中にあるあたたかさを知っているからこそ、そのやさしさをまた誰かに手渡すことができるのです。
成功とは、「受け取りながら、循環させる力」
このお手紙を通して、何度も繰り返しお伝えしてきたように、ビジネスも人生も、「循環」がすべての基本です。努力・感謝・報酬・共感・信頼。あらゆるものは、行きっぱなしではなく、「往復」で初めてエネルギーになります。
成功とは、与える力だけではなく、受け取りながら、流しながら、調和を保つ力なのです。
そしてそのためには、まず最初に、「自分がその循環の一部にふさわしい存在である」という、自己価値への静かな確信が必要になります。
受け取ることで、過去も未来も変えていける
「こんな私がもらっていいのだろうか」「与えるだけで、十分だと思ってきた」そう思ってきたあなたへ。
あなたが「ありがとう」と言って受け取ったその一歩は、もしかすると、あなたの家族、仲間、ご先祖、そしてこれから出会う誰かのための「許可」になるかもしれません。
受け取ることは、自分だけの話ではありません。受け取ることで、誰かの「遠慮」も、静かにほどけていくのです。
あなたには、もう「受け取る準備」ができています
最後に、あらためて、こう問いかけてみてください。「私は、受け取っていい存在だろうか?」その答えを、もう一歩、変えてみましょう。
「私は、受け取ることをゆるしていい存在だ」遠慮や不安のかわりに、あたたかい呼吸と、静かな感謝とともに、あなた自身の豊かさを、少しずつ受け取っていってください。
与えながら、受け取りながら、生きていく。その姿こそが、あなたという存在のまなざしに、いちばんやさしい光を宿していくのです。
このお手紙を書きながら、何度も「これはわたし自身へのメッセージだな」と感じていました。「受け取る」という行為は、思っている以上に繊細で、ときに勇気が必要で、ときに痛みもともないます。
でも、それを避け続けることは、自分という存在が、この世界から受け取るはずだった愛や信頼、喜びまでも手放してしまうことだったと、ようやく実感できるようになりました。
このお手紙は、誰かを説得するために書かれたものではありません。むしろ、すでに疲れてしまった誰かが、「もう、受け取っていいのかもしれない」と静かに思い出すためのものでありたいと思っています。
ここまで読んでくださったあなたが、もし少しでも心に風が通ったような感覚を持ってくださったなら、それは、あなたの中にある「受け取る力」が目を覚ましはじめた証かもしれません。
そして、あなたがこれから受け取るたくさんのものが、誰かのための優しさに変わっていくと信じています。
今日この場所で、言葉を受け取ってくださったことに、心から感謝を込めて。

編集後記
「受け取る力」というテーマは、単純な「行動のテクニック」だけでは語りきれない、非常に繊細で深いものだと改めて感じました。
多くの人が「もっと豊かになりたい」「愛されたい」と願いながら、実はその「受け取る器」が育っていないことに、どこかで気づいているのではないでしょうか。
私自身、「頑張って得ること」は得意でした。でも、「頑張らずに受け取ること」は、ずっと苦手でした。
なぜなのかをたどっていくと、そこには「自分には受け取る価値がある」という、とても静かで、でも根源的な「自己肯定感」の問題が横たわっていました。
このお手紙を書きながら自身の課題に向き合い、ご先祖セラピーの視点から「自分という存在の奥に流れる歴史」や「家系に流れる感情のパターン」を見つめなおすことは、実は「受け取ることを許すプロセス」だったのだと気づかされました。
豊かさとは、外側から与えられるものではなく、「受け取ってもいい」と思える内側の許可からはじまるものです。
このお手紙が、読んでくださったあなたの「受け取っていい」という静かな許可に、そっとつながっていくものであれば幸いです。
ご先祖セラピーに触れて「もう少し軽やかに知りたい」「日常の中で思い出していたい」と思ったら、ぜひ!こちらにも触れてみてください。
▼ Instagramでは、5匹のネコたちがやさしく語りかける「今日のひとこと」を毎日お届けしています。
▼ noteでは、感情の継承や家系の気づきについて、物語やエッセイの形で深掘りしています。
▼ アメブロでは、暮らしの中での気づきや、セラピーをもっと身近に感じられる日々の記録を綴っています。
それぞれの場所で、少しずつちがう「視点から、お伝えしています。
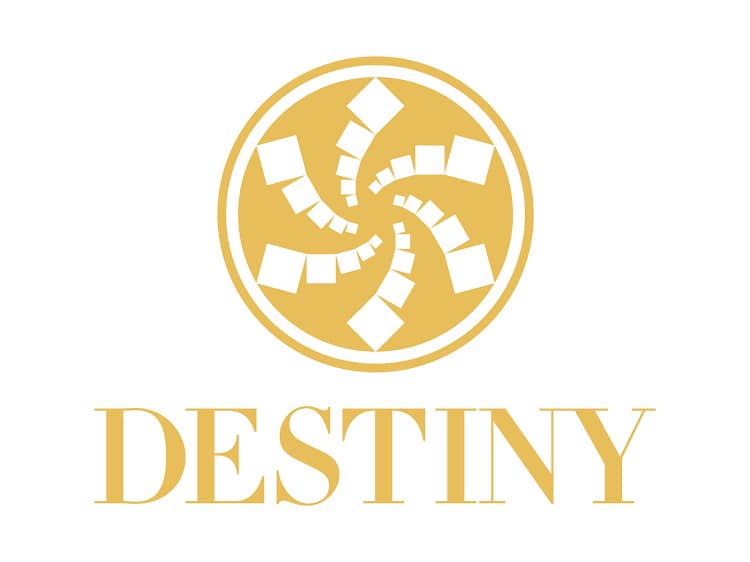
あなたとあなたの大切な人の人生が愛で満ち溢れるものであり続けますようにとの願いを込めてDESTINYからのお手紙をお届けさせていただいています。
「このテーマについて知りたい」
「こんなサービスがあったらいいな」
「今、こんなことで悩んでいます」
あなたの声をぜひ聴かせていただけませんか?