「ちゃんとやっているのに、うまくいかない」
「人のために尽くしているのに、報われない」
「いつもいい人でいたいのに、どこか満たされない」
そんなふうに感じている人は少なくありません。なぜなら、あなたの「性格」の問題ではなく、家系に根づいた「優しさの構造」が影響しているのかもしれません。
この記事では、「いい人であること」が持つ隠れたパターンと、私たちDESTINYのご先祖セラピーによってそれをどう見つめ直し、変容させていけるかを深掘りしていきます。

このお手紙を書こうと思ったのはDESTINY相談室に届いた1通のお手紙がきっかけでした。
++++++++++++++++++++++++++++++++
はじめまして。ずっと「いい人」でいようと頑張ってきました。
周りから頼られると断れないし、嫌われたくなくて、いつもニコニコしてしまいます。
でも最近、ふと気づいてしまったんです。
誰かに優しくするとき、心のどこかで「いつか報われたい」って思っていたことに。
本当は疲れてるのに、本当は助けてほしいのに、「大丈夫なふり」が当たり前になっていて、気づいたら、自分の気持ちがどこかへ行ってしまっていました。
怒るのも苦手、わがままも言えない、そんな自分がずっともどかしくてわたし。
このままでいいんでしょうか?
++++++++++++++++++++++++++++++++++
名前も書かれていないその手紙は、まるで今この文章を読んでいる「あなた」から届いたようにも思えました。
「NO」と言えないのは、優しさの証かもしれない
頼まれごとを断れない。本当は疲れているのに「大丈夫」と笑ってしまう。
自分のことより、つい他人のことを優先してしまう。
そういうあなたを、誰かは「優しい人」と呼ぶかもしれません。
でもその優しさが、自分をすり減らす理由になっているとしたら?
それはもう、見直すべき時が来ているのかもしれません。
「NO」が言えないこと。
それは決して「意志が弱い」わけでも「甘えている」わけでもありません。むしろ、あなたがどれほど「人とのつながり」を大切にしてきたかの証です。
でもその根っこには、こんな無意識の思い込みが隠れていることがあります。
「人に迷惑をかけたら、嫌われるかもしれない」
「自分勝手だと思われたら、仲間外れにされるかもしれない」
「ちゃんとしていない自分には、価値がないように感じる」
これらの恐れは、ただの思考ではありません。
もっと深いところ「大切なひとと生きるために身につけた防衛反応」でもあるのです。
その優しさは、あなたが選んだものですか?
「いい人」でいることは、周りとの摩擦を避け、環境を整え、秩序を保つためのスキルでもあります。
けれどそれが長く続くと、次第に「自分が何を感じているのか」がわからなくなってしまうことも...。
・相手が怒っていないか常に気になる
・頼まれると断れずに引き受けてしまう
・自分の感情より、相手の気持ちを優先してしまう
こうした状態が続くと、人生の主導権が「自分以外の誰か」の手にあるように感じてしまいます。
本来、優しさは「溢れるように湧き出るもの」。でもそれが「嫌われないための振る舞い」になっているとき、その優しさは、自分を守るための「仮面」になっていることもあるのです。
優しさの裏にあるもの
「優しくしなければ、受け入れてもらえない」
「役に立たないと、ここにいちゃいけない気がする」
「嫌われるのがこわくて、本音を隠してしまう」
それらはすべて、かつてのあなたが「大切な人と生き抜くために選んだ知恵」だったのかもしれません。
でも今、このお手紙を読んでくださっているあなたはもう、「誰かの期待に応えるためだけの優しさ」ではなく、「自分のために選び直す優しさ」へと、舵を切っていい時期に来ているのです。
そのとき、はじめて「境界線」という言葉が、冷たさではなく「温かい守り」として立ち現れてきます。

「優しさ」のルーツは家系にある
40代の女性経営者のご先祖セラピー中のひと言が、深く心に残っています
「わたし、怒った記憶がないんです。小さい頃から、笑っていたら怒られなかったから。それが、わたしの愛され方だったんだと思います。」
優しさのかたちには、個性があります。けれど、どこかに共通しているのは、「感情を抑えることで、愛されようとした記憶」です。
そしてその記憶は、多くの場合「自分ひとりのものではない」ことが、見えてくるのです。
家族のなかで「怒り」を抑え込んできた人たち
たとえば、あなたが「怒るのが苦手」「わがままを言えない」と感じるなら、それはあなた自身の「性格」ではなく、家系に流れる感情のルールが関係しているかもしれません。
ご先祖セラピーの時間の中で、こんなエピソードが語られることがあります。
「祖父は寡黙な人だったけれど、誰よりも働いて家族を支えてくれました」
「祖母は口数は少ないけど、嫁ぎ先でじっと我慢してきたと聞いています」
「母はいつも家族のために動いて、感情を出すのが下手な人でした」
こうした「怒りを抑える家族」のなかで育つと、子どもは自然とこう学びます。
「感情を出すと、空気が悪くなる」
我慢している人ほど立派だ、自分の気持ちを優先するのは「わがまま」
このようにして、「優しさ=自己抑圧」という構造が、無意識のうちに組み込まれていくのです。
ご先祖たちが選ばざるを得なかった「やさしさ」
歴史を振り返ると、私たちの祖父母・曾祖父母の世代は、戦争や災害、貧困や差別のなかを生き抜いてきました。
・戦後の混乱期、感情を殺してでも家族を守ろうと働き続けた祖父
・嫁ぎ先で従順にふるまうことで、ようやく居場所を得た祖母
・父や母の機嫌を損ねないように、空気を読みながら育った子どもたち
彼らは、「生き残るための知恵」として、怒りや悲しみを封じ、優しく、従順に、自己犠牲的にふるまうことを選びました。それは、必要な選択だったのです。
でも、今を生きる私たちが、同じやり方をそのまま繰り返す必要は、ありません。むしろ、もうその「優しさの仮面」を外していいというサインが、あなたの違和感や息苦しさとして現れているのかもしれません。
感情を抑えることが「愛される条件」になっていた?
「わたしは感情を表にだすことが苦手で……」と語る人の多くが、「感情を知られてはいけない」と思い込んでいたりします。
なぜなら、「感情を表に出す=トラブルのもと」だと家庭で学んできたから。そして、「黙ってがんばる人=評価される人」という構図のなかで育ってきたから。
たとえば…泣くと「そんなことで泣くな」と言われたり、怒ると「感じが悪い」と注意されてしまったり。
落ち込むと「人前でそんな顔するな」と否定された...そうして、感情を見せることに罪悪感を抱いたまま、大人になった私たちは、自分の本音にさえフタをしてしまうのです。
家族の物語は、無意識の「脚本」になる
心理学では、「スクリプト(人生脚本)」という考え方があります。
幼い頃に繰り返し経験した感情や、人間関係のパターンが、その人の人生全体に影響を及ぼしているというものです。そしてその脚本は、多くの場合「家族の中で繰り返されてきたこと」です。
・祖母→母→自分と続く、「我慢強い女性の人生」
・父→兄→自分と続く、「感情を表に出さない男性の人生」
・祖父→父→自分と続く、「一人で抱え込む責任感の連鎖」
こうした流れがあることに気づくと、「自分だけの問題じゃなかったんだ」と深いところで腑に落ちる瞬間が訪れます。
優しさは悪くありません。でも、その優しさが「誰のものだったのか」に気づくことは、とても大切です。
・母から受け継いだ「自分を後回しにする優しさ」
・祖母から受け継いだ「口を閉ざして微笑むこと」
・父の背中から感じてきた「感情を見せない強さ」
それらを「そうするしかなかった時代背景」とともに理解したとき、はじめて、その優しさを「自分のものとして選び直す」ことができるようになるのです。

共感しすぎる人の心のしくみ
「相手がつらそうにしていると、自分のことのようにしんどくなる」
「何か言い返されるだけで、頭が真っ白になる」
「相手の気持ちを先に察しすぎて、自分が何を感じているのかわからなくなる」
こうした感覚を抱く人は少なくありません。共感力が高いことは、感受性の高さや優しさの表れです。けれど、「共感しすぎる状態」は、知らず知らずのうちに、自分を消耗させてしまうのです。
共感のセンサーが強すぎると起こること
共感とは、本来、相手の感情を自分の内側で感じ取り、理解しようとする能力です。けれど、そのセンサーが敏感すぎると、次のような現象が起きます。
・他人の感情を、自分のものと区別できなくなる
・相手のつらさを、まるで自分が体験しているかのように感じる
・相手の言動に「過剰に反応」してしまう
これは、脳のミラーニューロン(共感細胞)や神経系の特性によるものでもありますが、多くの場合、それ以前に育った環境によって「共感が戦略になっていた」ことが背景にあります。
たとえば、こんな幼少期の記憶がある人はいないでしょうか。
・親の機嫌を先に察して、行動を選んでいた
・家の空気がピリついていると、息をひそめていた
・兄弟や家族のトラブルに挟まれ、和ませ役を演じていた
こうした環境では、「共感すること=生き残る術」
だからこそ、共感力は単なる性質ではなく、「身につけざるを得なかった感情のスキル」でもあるのです。
「感じること」と「背負うこと」は違う
ここで大切なのは、共感と同一化を切り分ける視点です。
「共感」とは、相手の感情に寄り添い、「理解しようとする」姿勢。
同一化とは、相手の感情を自分のものとして「引き受けてしまう」状態。
共感はつながりを生みますが、同一化は境界線をあいまいにします。
結果として、自分がどこまでなのか、どこからが他人なのかがわからなくなり、疲弊、混乱、無力感といった「エネルギーの漏れ」が起こってしまうのです。
自分の感情がわからなくなるメカニズム
共感しすぎる人は、他人の感情に集中するあまり、自分の感情のスペースがなくなっていきます。
「こう言ったら相手はどう思うだろう」
「この空気を壊したくないから、笑っておこう」
「私はどうしたいか」ではなく、「あの人がどう思うか」で動く
このように、常に「他者基準」で思考や行動が決まると、やがて「自分が何を感じているのか、何を望んでいるのか」がわからなくなってしまいます。
これは、感情の「切断」であり、長く続くと「麻痺」のような状態になります。そしてそれが、自分らしい選択や直感を妨げる原因にもなるのです。
感情にもまた、物理的なスペースと同じく、「健全な境界」が必要です。
相手の痛みに共感しながらも、それを「自分のもの」にしない。相手の期待に寄り添いながらも、「自分の真実」を守る。相手を理解しようとしながらも、「わからない」ことを許す
このような境界があるからこそ、共感は「共倒れ」ではなく、「支え合い」に変わります。境界がなければ、どんなに優しい心も、自分を失う方向に使われてしまうのです。
共感の力を「選んで使う」
DESTINYの「共感」の定義は、感情を「自分の軸」で扱える状態です。それは、感じすぎることを否定するのではなく、「今、自分は何を感じているか」「これは自分の感情か、他人のものか?」を冷静に見つめる視点を持つこと。
すると、共感力は「境界を溶かすもの」ではなく、「つながりの質を高めるもの」へと変化します。
共感力の高い人ほど、「ひとりで抱える力」も強くなります。
それは、わかってほしいのに、誰にも伝えられなかった経験があるからです。
「つらさを言葉にしても気にしすぎと言われた」
「感じたことを否定されて、自分の感性に自信がなくなった」
「誰かの期待に応えることで、存在価値を保ってきた」
こうした記憶があると、人とつながることに「恐れ」が混ざります。そして、孤独の中で「共感しすぎる自分を責める」という悪循環が生まれてしまうのです。
でも、本当はその共感力こそが、あなたの優しさの証であり、心の繊細な感受性の美しさなのです。
大切なのは、その優しさを「自分のためにも使う」こと。それができたとき、あなたの共感力は、自己犠牲ではなく「真のつながり」を育む力へと変わっていきます。

家系図で読み解く「優しさの構造」
共感しすぎる。NOが言えない。人との境界線があいまいになる。
それらは、単なる性格や性質だけではありません。むしろ、家族というシステムの中で、無意識に「役割」として引き受けてきた優しさの形かもしれません。
家系の中には、「こう振る舞えばうまくいく」「こうしてはいけない」といった、「目に見えない感情のルール」があります。
そしてそのルールは、驚くほど正確に、次の世代へと受け継がれていくのです。それを読み解く手法のひとつが、「ジェノグラム」です。
ジェノグラムとはなにか?
ジェノグラムとは、簡単に言えば感情や関係性のパターンまで可視化できる家系図です。
通常の家系図が血縁を表すものだとすれば、ジェノグラムはそこに以下のような要素を加えていきます。
・各人物の性格や感情の傾向
・家族間の関係性(親密・断絶・依存・支配など)
・くり返されてきたパターン(離婚・早逝・病気・経済的困難・不登校など)
・特定の役割(犠牲者・仲裁者・ヒーロー・問題児など)
この図を使って両親の高曾祖父の代まで俯瞰してみると、「同じような出来事や感情の傾向が、驚くほどの精度で繰り返されている」ことに気づくことがあります。
実際のジェノグラム例「優しさ」の継承
たとえば、ある女性のケースを見てみましょう。
Nさん(40代・美容サロン経営)
「人に頼まれると断れない」「感情を出すと罪悪感を感じる」「家族内ではいつも聞き役」
ジェノグラムをたどると─
・母 いつも「穏やかに見えるが怒らない」、不満を言わず体調を崩す。
「ごめんね、こんなお母さんで」が口癖。
・祖母 戦時中に夫を亡くし、女手一つで子どもを育てた。
「人に迷惑をかけてはいけない」が口癖。
・父 厳格で無口、家庭内で感情表現を好まない。
「泣くな、弱さを見せるな」がしつけの基準。
この家系の中には、「怒りや悲しみは隠すべきもの」という強い感情のルールがありました。
Nさんが「やさしい人」でいようとしてしまうのは、「自分らしさ」ではなく、「生き残るために家族が受け継いできた戦略」だったのです。
ジェノグラムで見えてくる「役割の連鎖」
家族の中で、繰り返し現れる「役割」があります。たとえば、
・「犠牲者役」家族の平和のために自分を抑えて尽くす
・「仲裁者役」家族の衝突を避けるために空気を読む
・「ヒーロー役」家族の期待を一身に背負い成果を出す
・「問題児役」家族の抑圧された感情を代弁するかのように問題行動を起こす
これらの役割は、家族内のバランスを保つために「無意識に誰かが引き受ける」ものです。
そして、ある役割が強く繰り返されている家系では、次の世代にも同じ力学が作用しやすくなります。
自分の優しさは、「自分のもの」か?
あなたの優しさは、どこから来たものでしょうか?
自分の意思で選んだやさしさ。
愛されるために演じたやさしさ。
家族の空気を壊さないために覚えたやさしさ。
親の感情を背負わないために習得したやさしさ。
ジェノグラムを描きながら、ひとつずつ問い直してみてください。その答えの中に、「今あなたが繰り返している生き方の起源」が眠っています。
ジェノグラムで「構造」を知ると、「感情」が整理される
感情は、たんに「湧き上がるもの」ではありません。背景があり、文脈があり、継承があります。
ジェノグラムは、感情の「背景」を可視化し、混乱を整理するためのツールです。
「なんで私はいつもいい人になってしまうのか?」
「なぜNOが言えないのか?」
「どうして他人の感情に巻き込まれやすいのか?」
これらの問いに、頭ではなく「構造」で答えてくれるのが、ジェノグラムなのです。構造が見えたとき、「わたしが悪かったわけじゃない」という深い安心感が生まれます。
変えるのは「性格」ではなく、「構造」
私たちは、自分の「性格」を変えようと努力しがちです。でも実際には、変えるべきなのは「構造」です。
・家系の中で暗黙に受け継がれてきたルール
・感情を封じることで維持されていたバランス
・誰かが無意識に背負ってきた痛みの連鎖
それらに気づき、言葉にして、そっと手放すこと。それが、「私」という存在を「役割」から解放する第一歩なのです。

「存在としての優しさ」を取り戻す3つのステップ
「役割」としての優しさから、「存在」としてのやさしさへ。
これまでは、あなたの中にある「優しさ」が、家族や家系に流れる「感情の構造」から生まれていたことを見てきました。つまり、あなたが「いい人でいよう」としてきたのは、単なる性格ではなく、「受け継がれたサバイバルの知恵」だったということ。
では、そこからどうやって「自分自身のやさしさ」を取り戻していけばよいのでしょうか?DESTINYでは、そのための実践として、次の3ステップを提案しています。
STEP1 「受け取る」
「私はずっと、優しくいようとしてきた」と認める。
多くの人が、「自分は我慢ばかりしていた」「もっと本音で生きたかった」と語ります。でも、その前に必要なのは、「これまでの自分を責める」のではなく、「ねぎらう」ことです。
ずっと空気を読んで、場を和ませてきた。
人に頼まれると断れず、自分を後回しにしてきた。
自分の感情より、誰かの気持ちを優先してきた。
そのすべては、「誰かを大切にしたい」「関係を守りたい」からだったのではないでしょうか。
まずはその優しさを、「がんばってきた自分の証」として受け取ること。
「そのままの自分」に「ありがとう」と言ってあげること。そこからしか、本当の変化は始まりません。
STEP2 「ほどく」
「誰のための優しさだったのか?」と問いかける
自分が抱えてきた優しさを「誰のために選んだのか」を見つめ直します。
・母が不安定だったから、自分は「しっかり者」でいようとした
・父が厳しかったから、自分の意見を隠すクセがついた
・家族の衝突を避けるために、ずっと「調整役」だった
こうして思い出していくと、自分の優しさには「背景」があることに気づきます。
それが「誰かのために自分を抑えるやさしさ」だったとしたら、もうそれを「自分自身のもの」として無条件に抱える必要はないのです。
そのやさしさは、あなたのものですか?それとも、誰かのために選ばされた「役割」ですか?
STEP3「選び直す」
「今の私にとっての本当のやさしさとは?」と定義する
過去の優しさをねぎらい、背景を理解したら、最後にそれを「今の自分の視点」で「選び直す」ことができます。たとえば、
「本当につらいときは助けを求めてもいい」
「NOを言うことは、相手を大切にしないことではない」
「自分の気持ちを最優先しても、人に愛されていい」
優しさは、「人のためだけのもの」である必要はありません。
自分の軸を守りながら、人とつながるやさしさも、確かに存在していいのです。
それが「境界を持ったやさしさ」。
つまり、「自分を犠牲にしない共感」というあり方です。
選び直したとき、人生が変わりはじめる
この3ステップを経て、優しさを「自分の手」に取り戻した人たちは、次のような変化を教えてくれます。
「断ることに罪悪感がなくなってNOと言えるようになりました。」
「表面的なつながりに疲れなくなったと同時に、人間関係が広がり嬉しいです。」
こうした変化は、感情の統合によって起きる「構造のシフト」です。それは、環境を変えるのではなく、「自分の在り方」を変えることから始まります。
「本当の優しさ」は、自分も人もあたためる力に変えられる
「役割」としての優しさを手放し、「存在」としてのやさしさを選び直す。
それは、自分を守ることで、人とも健やかに結びなおすという「境界ある共感」への転換です。
やさしくするために、自分を犠牲にしなくていい。
わたしが満たされることで、初めて本物のやさしさがにじみ出る。
やさしさは、与えすぎるものではなく、選んで届けるものへ。
そのとき、あなたの優しさは、無理をしない、見返りを求めない、「自分自身の軸」から生まれる、しなやかな力に変わっていきます。

優しさと自立・共感しながら自分を守る方法
「境界線」があるからこそ、やさしさは長く続く。
優しさは、本来とても美しい力です。けれどそれが、「自分をすり減らすもの」になっているとしたら...。
それは、やさしさに「境界」がない状態かもしれません。
ここで大切になるのが、共感と自立のあいだにある「境界の技術」です。
他人に心を向けながら、自分の軸を守る。優しさを表現しながら、自分を犠牲にしない。
共に感じながら、過剰に同一化しない。
それは冷たさではなく、「自分も大切にする」ための土台です。
境界線とは、「冷たくなること」ではない
「境界線を引く」と聞くと、「人に冷たくすること」「距離をとること」「壁をつくること」だと感じる人もいるかもしれません。
でも本当は、境界線とは「自分の感情と他人の感情を分けること」。そのうえで、「自分が選べる」ようになることです。
・今、それは私の課題なのか?
・その感情は、自分のものか、誰かのものか?
・私は、本当に助けたいのか?それとも罪悪感から動いているのか?
これらの問いが、自分の中の「境界感覚」を育ててくれます。
「断る力」と「受け取る力」はセット
優しさが深い人ほど、断るのが苦手です。でも、境界線を育てるうえで最も大切なのは、「断ること」ではなく、「選ぶこと」です。
「私はこの依頼を引き受けたいのか?」
「この人の期待に応えることで、私はどう感じるか?」
「断ることは、拒絶ではなく誠実なのでは?」
断る力は、受け取る力とセットです。
「NO」が言えるからこそ、本当に必要なものを「YES」で迎えられるのです。
そしてそれは、相手を尊重することでもあります。
「なんでも受け入れる」のではなく、「自分の内側と相談して応じる」。
それこそが、信頼に根ざした境界のあり方です。
境界線があるから、感情が腐らずに済む
境界がない状態では、自分の本音を飲み込み続けることになります。
そうすると、どうなるか?
疲れても「大丈夫」と言ってしまう、不満がたまっても「いいよ」と受け入れてしまう。本音を隠すクセが抜けなくなることも...。こうして抑え込んだ感情は、表面では「優しさ」に見えても、内側では徐々に「わかってもらえない怒り」や「存在の寂しさ」へと変化していきます。
感情は、抑え続けると「腐る」のです。
だからこそ、健やかな優しさには、「排水路」のような境界線が必要です。
必要のない感情は流し、必要な気持ちはすくい上げる。それが、長く続くやさしさの「水路」を整えるということなのです。
愛しながら離れる、という選択肢
私たちは、「大切な人だから、そばにいないといけない」と思いがちです。
けれど、愛するということは、必ずしも「距離を詰めること」ではありません。ときに、離れることが最も誠実な愛のかたちであることもあります。
助けたい気持ちが、自分の限界を超えてしまうとき、共感しすぎて、相手の人生まで引き受けてしまいそうなとき。距離を置かないと、自分の気持ちが見えなくなるとき。
そんなときは、「近づかないこと」も優しさです。
やさしさとは、「そばにいること」だけではありません。「自分のままでいられる距離を知ること」も、愛の知恵です。
自分を守るから、ほんとうに優しくなれる
自分の感情を守るということは、わがままになることでも、無関心になることでもありません。
それは、「自分の心に誠実でいる」こと。その誠実さが、やさしさの「質」を変えてくれます。
無理をしなくなることで、見返りを求めなくなる。
自分の気持ちを大事にしたうえで、相手にもやさしくなれる。この状態が、「境界のある共感」です。
「わたしはわたし、あなたはあなた」
だからこそ、本当につながりあえる。やさしさと自立は、決して反対の概念ではありません。それはむしろ、「自分という土台」を持っているからこそ育てられるものなのです。
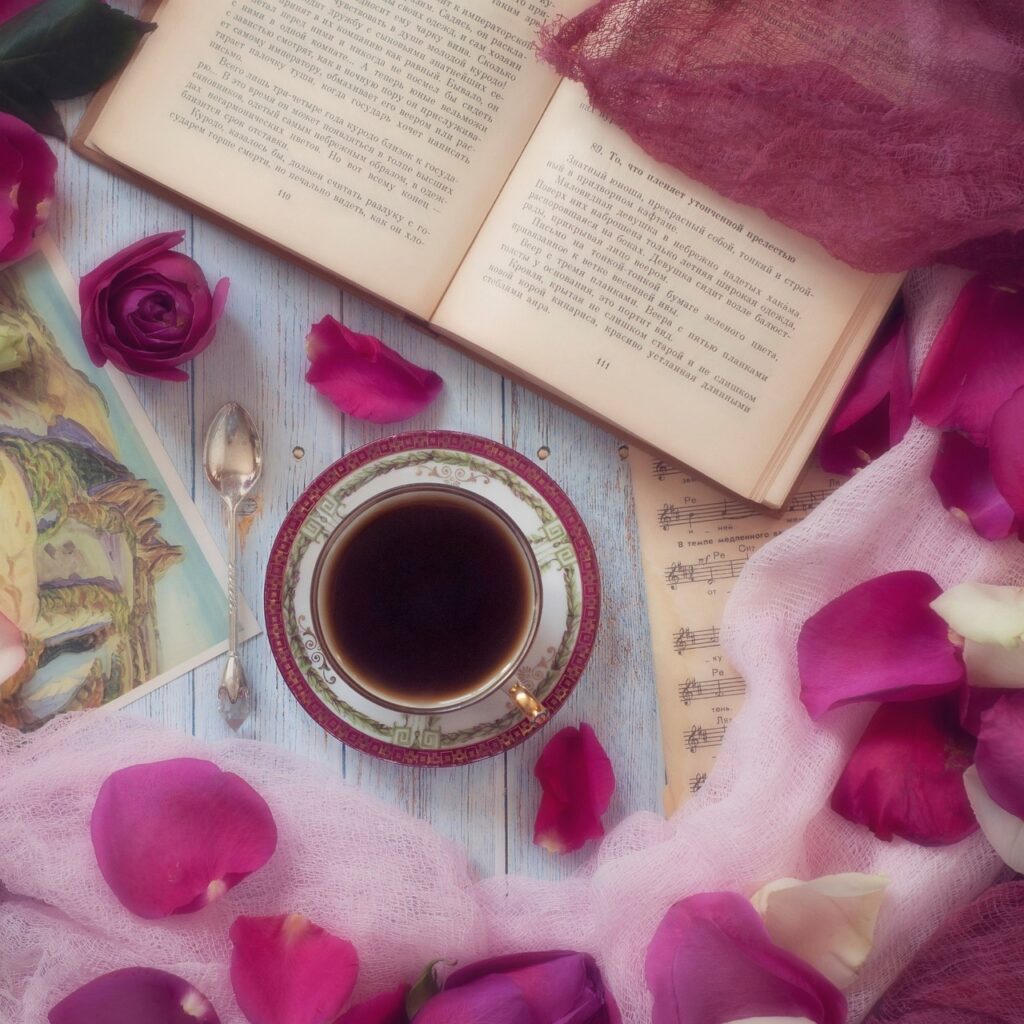
ケーススタディ「変容の記録」
「いい人」という仮面を外したとき、人生は動き出す
ここまで、「優しさ」の裏側にある構造を見つめてきました。
家系に刻まれた「感情のルール」、共感しすぎる人の心の仕組み、そして「自分のために優しくなる」ための実践ステップ。
では、実際にこのプロセスを経て変容した人たちは、どのような気づきを得て、何を手放し、どう人生を選び直したのでしょうか?DESTINYの「ご先祖セラピー」を体験してくださった3名のケースをご紹介します。
case1「強くて優しい姉」を演じていたMさん(40代・看護師)
Mさんは、3人姉妹の長女として育ち、幼い頃から「いい子」「しっかり者」と言われてきました。
母親は情緒不安定で、家庭の空気を壊さないよう、Sさんは常に「大丈夫な自分」を演じていました。
社会人になってからも、周囲に気を配り、頼まれると断れず、仕事でも家庭でも「調整役」。
表面上は穏やかでも、内側では「いつまで頑張り続ければいいの?」という限界を感じていたそうです。
ジェノグラムを描きながら家族の歴史を振り返ると、祖母もまた、戦後の混乱の中で「献身的に家族を支え続けた女性」でした。
「わたしの優しさは、ただの性格じゃなくて、役割だったんだ」
そう気づいた瞬間、Mさんは涙を流しました。その後、休職を経て、家族との関係を少しずつ見直し、「弱さを見せる練習」「断る練習」「頼る練習」を重ねていきました。
「優しいままでも、自分を大切にしていい」そう思えたとき、人生が静かに動き始めたんです。
case2「NO」が言えなかったKさん(30代・フリーランス)
Kさんは、自分の感情を伝えるのが苦手で、人間関係でも恋愛でも「相手に合わせてしまう」クセが抜けませんでした。
「嫌なことがあっても我慢する。自分がどうしたいかより、相手がどう思うかを優先してしまう」
Kさんの家系には、父方に「感情を表現しない男性」が多く、母方には「空気を読む、従順な女性」が何世代にもわたって連なっていました。家系図に線を引きながら、こうした「感情の圧縮パターン」が見えてきたとき、Kさんはひとつの問いを立てました。
「このやさしさは、本当にわたしが選んだものだったのかな?」
その後、Kさんは小さなところから練習を始めました。
・「今日は行けない」と言ってみる
・誘いを断るときに理由を説明しすぎない
・相手の期待と、自分の気持ちを分けて考える
すると、「嫌われなかった」という経験が少しずつ自信になり、本音で関われる人間関係が増えていきました。
case3「いい父親」の仮面を外したTさん(50代・経営者)
Tさんは、社員や家族にとてもやさしい人でした。
常に気を配り、怒らず、誰に対しても公平であろうと努めてきました。けれど、内面には「本当は言いたいことが言えない」「孤独を誰にも見せられない」という苦しさを抱えていました。
「怒りたくても怒れない。それを大人の対応って言い聞かせていたけど、本当はただ、怖かったんだと思う」
Tさんの父親は厳格で、家庭では感情を一切見せない人でした。
「男は感情を見せるな」「責任を果たしてこそ存在価値がある」そんな無言のルールが、代々続いていたのです。
ご先祖セラピーを通してTさんが気づいたのは、「自分のやさしさは、怒りを封じることで得た仮面だった」ということでした。
その後、Tさんは家族に本音を少しずつ話しはじめました。怒りではなく、素直な寂しさや不安を共有することが増え、家庭内の会話の質も、驚くほど変化したそうです。
「優しさの正体」が見えたとき、癒しは始まる
3人に共通していたのは、
・優しくあることが「無意識のルール」になっていた
・それが「家系の中で必要とされた生き方」だった
・本来の自分を取り戻すには、まず「ねぎらい」が必要だった
という点でした。そしてなにより、彼らが人生を変えられた理由は、「優しさを否定した」からではなく、「優しさを自分の意思で選び直した」からです。
優しさを「選べる」人になるということ
優しさを選べるということは、「断ること」も「離れること」も「NOを言うこと」も「愛のかたちのひとつ」として扱えるようになるということです。それは、他人の期待に合わせる生き方から、「自分の心に誠実でいる」人生へのシフトです。

優しさのギフトを「自分の色」に塗り直す
もう、誰かのためのやさしさじゃなくていい。
これまで見てきたように、「優しさ」は、ときに「役割」として身につけてきたものでもあります。
けれどその優しさは、あなたの中で、きっとずっと大切にされてきた感覚でもあるはずです。
誰かの痛みに気づけることや、空気の微細な変化を感じ取れることも。
そして、相手の言葉の裏にある本音に、そっと寄り添えることだって。
そんな繊細さとあたたかさは、あなたの中にあるご先祖からの愛のギフトです。だからこそ、もう一度、問い直してみませんか?
「わたしは、どんな優しさを生きたい?」
「与えるだけ」から「選んで届ける」優しさへ
過剰に優しさを与えすぎる人の多くが、「自分が我慢すればいい」と思ってきました。
でも、優しさは「与えるだけ」では、循環しません。
与えることと同じくらい、「受け取ること」も「選ぶこと」も大切なのです。
「この人とは、どんな関わり方が心地いい?」
「わたしは、どう在りたい?」
「この優しさは、ほんとうに必要なもの」
こうした「自分への問いかけ」を通して、優しさの使い方が変わっていきます。
「誰のため」でもなく、「義務」でもなく、「わたしが選んだ」という意識で届けられた優しさは、やがてあなた自身もあたためてくれるようになるのです。
受け継いだものに感謝して、「自分の色」に塗り替える
たとえば、
「祖母から受け継いだがまん強さ」を、「静けさと包容力」へ。
「母から受け継いだ気配り」を、「感受性と観察力」へ。
「父から受け継いだ責任感」を、「誠実さと信頼」へ。
このように、受け継いだ優しさの「エネルギー」を、自分の意志で再定義していくことができます。
誰かのために選んだ生き方を、「わたしの選択」として、再びこの手で塗り直していく。
それは、過去を否定することではありません。
むしろ、「感謝と誇り」をもって、未来を選び直すという行為です。
もう、役割として生きなくていい
「いい人」じゃなくても、あなたには価値があります。誰かの期待に応えなくても、あなたは十分すぎるほど、存在そのものが尊いのです。優しさを、もう「評価されるための道具」として使わなくていい。
感情を抑えなくてもいいこと、我慢しなくてもつながれる、本音を出しても、愛されていい。
それを、まず「自分が」信じること。そこからすべてが変わっていきます。
これからのあなたが届けるやさしさは
あなたが本当に自分の気持ちを受け入れ、必要な人に、必要なときに、「自分の言葉で、自分の歩幅で」届けるや優しさは、きっと、誰かの人生を照らします。
そして、それは同時に、あなた自身の命の輪郭を照らしていくのです。優しさとは、「誰かのため」だけではなく、「自分らしくあるための力」でもあります。

編集後記
「いい人でいなきゃ」その思いは、きっと誰かを大切にしたかったから。
けれど、もしもその優しさが、あなた自身をすり減らす理由になっていたとしたら。
それはもう、「愛のかたち」を見直すタイミングかもしれません。
DESTINYのご先祖セラピーでは、一見美徳に見える「優しさ」が、
実は「家系の中で繰り返されてきた、痛みの知恵」であることを丁寧に紐解いていきます。
過去を責めるのではなく、未来の自分に「やさしさを手渡すため」に。
あなたが自分自身の優しさを、選び、守り、誇れるようになったとき。あなたの優しさは、人を救いながら、自分もあたためてくれる光に変わっていきます。
次回は、「家系とお金、受け取る力を妨げる記憶のブロック」について、豊かさを遠ざけてしまう無意識のルールをテーマにお届けします。
ご先祖セラピーに触れて「もう少し軽やかに知りたい」「日常の中で思い出していたい」と思ったら、ぜひ!こちらにも触れてみてください。
▼ Instagramでは、5匹のネコたちがやさしく語りかける「今日のひとこと」を毎日お届けしています。
▼ noteでは、感情の継承や家系の気づきについて、物語やエッセイの形で深掘りしています。
▼ アメブロでは、暮らしの中での気づきや、セラピーをもっと身近に感じられる日々の記録を綴っています。
それぞれの場所で、少しずつちがう「視点から、お伝えしています。
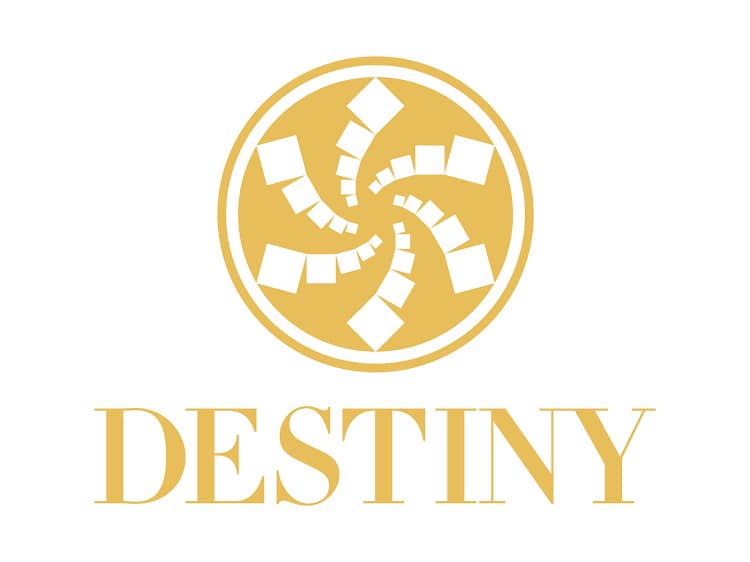
あなたとあなたの大切な人の人生が愛で満ち溢れるものであり続けますようにとの願いを込めてDESTINYからのお手紙をお届けさせていただいています。
「このテーマについて知りたい」
「こんなサービスがあったらいいな」
「今、こんなことで悩んでいます」
あなたの声をぜひ聴かせていただけませんか?
https://docs.google.com/forms/d/1cmI3soV5IdmhqFvLVkQw0pNYEtJqS07syR2NuVXk0xk/edit
この記事は、多くの人が感じる「いい人でいること」の悩みを深く掘り下げています。特に、家系に根づいた「優しさの構造」がどのように個人の感情や行動に影響を与えるかを分析している点が興味深いです。自分自身の感情を抑え、周りの期待に応えることが当たり前になっている人にとって、この記事は新しい視点を提供してくれるかもしれません。しかし、この「優しさの仮面」を外すことが本当に自分にとっての自由につながるのか、疑問に思います。共感しすぎることが自分を消耗させてしまうという指摘は確かにその通りだと思いますが、共感力を完全に抑えることが解決策なのか、それともバランスを取ることが重要なのか、もう少し詳しく知りたいです。