「ぼくが みんなの 目に なろう」
──『スイミー』(レオ・レオニ)
たくさんの想いが、名もなきままに、静かに受け継がれている。
誰かが見つめてくれていたこと。
誰かの中に、自分がいたこと。
そんなふうに、気づかれずに「続いてきた記憶」が、わたしたちの内側でそっと息づいていることがあります。
DESTINYの哲学における「やすらぎ」とは、静けさの中に宿る「つながりの証」を指します。
その余韻は、個人の心をやさしく包み込み、ときに人生の選択に、確かな「うなずき」を与えてくれる。
この「やすらぎの余韻」を手がかりに、私たちがどのように感情を扱い、統合し、そして「家系」という無意識の流れと向き合っていけるのかを、このお手紙では論理と実践の視点から丁寧にたどっていきます。

やすらぎとは「処理された感情の残響」
私たちは日々、さまざまな感情を経験しています。怒り、哀しみ、不安、焦り、安堵、よろこび...そのどれもが、瞬間的に現れては過ぎ去っていくように見えます。
しかし実際には、過去に処理しきれなかった感情が、「未完了のまま」心のどこかに残っていることがあります。そのような未処理の感情は、思考を曇らせ、意思決定にブレーキをかけてしまいます。
「なぜかわからないけれど、動けない」「理由なく、疲れている」
その背後には、気づかれないままに残された「感情の残響」が潜んでいる可能性があります。
感情とは、経験と記憶を通じて心に刻まれた「反応」です。
その反応が未整理なまま蓄積されると、やがてノイズとして表面化します。
たとえば
• 人前で発言するたびに、なぜか胸が締めつけられる
• 上司の表情を見ただけで、必要以上に萎縮してしまう
• 良いニュースが届いても「素直に喜べない」感覚がある
こうした反応は、今この瞬間の出来事に反応しているようでいて、実は過去に「処理されなかった何か」が揺り起こされていることが多いのです。
やすらぎとは「整理された感情のあと」にしか現れません
私たちは「癒し」や「やすらぎ」を求めて、休日に出かけたり、瞑想やアロマ、音楽に触れたりします。もちろんそれらは、疲れた心をいたわるうえでとても有効です。けれど一方で、表層的なリラクゼーションでは届かない「深部のノイズ」が存在します。
それは、自分でも意識できていないほど古い、けれど確実に残っている「感情の断片」です。
「ノイズ」が静まって初めて、心には「余白」が生まれます。この「余白」こそが、「やすらぎ」の正体です。
つまり、「やすらぎ」はただ与えられるものではありません。なぜなら「やすらぎ」は、私たち自身が、感情に気づき、感情を認め、感情を手放すというプロセスを通して、「結果として訪れる状態」だからです。
「納得した感情」は、静かな強さに変わります
「やすらぎ」についてお伝えする上で、忘れてはいけない大切な視点があります。
それは「感情の処理」とは、感情を排除することではありません。むしろ、感情自体に名前を与え、居場所をつくってあげることです。
たとえば、幼い頃の「さみしさ」に気づき、「あのとき、私はちゃんと孤独だったんだ」と認められた瞬間、その感情は「納得」というかたちで統合されていきます。
否定でも肯定でもない。「そうだったね」と言ってあげること。そのプロセスを経ることで、かつての「痛み」は「語れる経験」へと変わります。不思議なことに、そうして統合された感情は、誰かの安心感にもつながっていきます。
未処理の感情は、周囲をざわつかせますが、統合された感情は、周囲にやすらぎを与えるのです。

感情の処理と統合は、重要な「ビジネススキル」でもあります
リーダーや経営者にとって、「感情を扱う力」は思っている以上に重要です。それは、他者の感情に対する配慮という意味だけではありません。むしろ大切なのは、「自分自身の感情が、判断を歪めていないか」という問いを持てることです。
• 焦っているときに即断しない
• 怒りの裏にある恐れを見抜く
• 不安が「何に反応しているのか」を分解する
こうした感情のメタ認知ができる人は、判断力にブレが少なく、チーム全体にも静けさをもたらします。つまり、「やすらぎのある人」は、戦略的にも強いのです。
やすらぎとは、内なる感情が静かに整った状態
私たちは、何かを変えるために「行動」や「意志」に頼りがちです。けれど、その土台にはいつも「感情」があります。感情を処理すること、感情を抱きしめること。そして、感情とともに静かに生きること。このプロセスの積み重ねの先に、はじめて「やすらぎの余韻」は訪れます。
それは「終わった過去」ではなく、今を支える、もう一つの静かな記憶です。
家系的記憶としての「静かな影響」
感情は、個人の内側だけで生まれているものではありません。実は、私たちの思考や感受性には、過去の世代、とくに家族やご先祖の感情的な経験が、静かに影響を与えていることがあります。
それは、大きな出来事やドラマではなく、むしろ「語られなかった記憶」や「説明されないままの感覚」として、代々受け継がれていくのです。
なぜ「語られないもの」が残るのか
たとえば、祖父母の代で起きた戦争体験や、親世代で繰り返された家族内の不和、あるいは女性たちに強く求められてきた「我慢と犠牲」の文化。これらは、必ずしも明確な言葉や記録で伝えられるわけではありません。
けれど、子どもたちは「空気」や「表情」「口にされない沈黙」を通して、それを感じ取り、内面化していきます。そして、そうした“未処理の感情”が家系全体に沈殿するように、後の世代に無意識の影響を与えるのです。
家族文化がつくる「やすらげない体質」
このような家系的影響は、とても静かで、気づかれにくいものです。たとえばこんな形で現れることがあります。
・「安心」を感じることがうまくできない
・リラックスすると「怠けている」と感じてしまう
・家族の中で「静かにしていること」が美徳だった
・感情を出すと「わがまま」と言われて育った
こうした文化的な背景があると、「やすらぎ」や「くつろぎ」を感じる力そのものが育ちにくくなります。それどころか、「がんばる」「耐える」「役に立つことが価値」というメッセージばかりを受け取り、静けさや安心を「怖いもの」のように感じてしまう人もいるのです。
やすらぎの記憶をたどるということ
「家系的記憶としての静かな影響」とは、まさにこうした「目に見えない感情の連鎖」に気づいていくことです。
たとえば、
・なぜかいつも、何かに追われるような感覚がある
・自分に優しくしようとすると、罪悪感を覚える
・幼少期の記憶よりも、祖母の姿がなぜか印象深い
これらは、自分の感情というよりも、「家の空気」や「血筋の感受性」に由来している可能性があります。
ご先祖の誰かが言えなかった「さみしかった」という一言。
母親が飲み込んだ怒り。祖父が誰にも言わずに背負ってきた責任感。そういった感情は、沈黙のまま次の世代に「語られていないまま」届きます。そして、受け取った側がその存在に気づいたとき、ようやく「癒しの連鎖」が始まるのです。
家系の記憶に触れることは、自分に静けさを取り戻すこと
家系的な記憶に触れるということは、「過去を振り返って苦しむこと」ではありません。むしろ、それは「自分のやすらぎを取り戻す鍵」を受け取ることでもあります。どんな家系にも、必ず「守ってきたもの」があります。
不器用でも、静かでも、遠回しでも。感情を抱えながらもつないできてくれた何かがあるのです。その想いを静かにたどりながら、「これはもう受け継がなくていい」と気づくものと、「これは大切に持っていたい」と思えるものに分けていく。
それが、「感情の継承」から「統合」への第一歩です。

感情の統合プロセス・ビジネスパーソンに必要な「静寂の時間」
ここまでは「感情の未処理が生むノイズ」と、「家系的に受け継がれる静かな影響」についてお伝えしました。
では実際に、こうした感情をどのように扱い、「やすらぎの余韻」へとつなげていくのでしょうか。
その鍵になるのが「感情の統合プロセス」です。
感情は「気づく→認める→手放す」の3ステップで整っていく
感情を扱う基本的なプロセスには、3つのステップがあります。
- 気づく・今どんな感情が自分の中にあるのかに意識を向ける
- 認める・その感情に「理由がある」ことを受け入れる
- 手放す・自分の中で抱えていた意味を問い直し、離していく
このプロセスは、心の中で繰り返される「対話」のようなものです。特別な道具も、テクニックも必要ありません。大切なのは、「丁寧に向き合う時間」と「自分を裁かない姿勢」です。
なぜビジネスに「静寂」が必要なのか
ここまでの話を読んで、「感情とビジネスは関係ない」と思われる方もいるかもしれません。しかし実際には、リーダー層や意思決定者ほど、感情の影響を大きく受けています。
・焦りからくる短絡的な判断
・期待を裏切られることへの恐れ
・自分の存在価値を守ろうとする反応
こうした「感情由来の選択」は、ビジネスにおいて大きな損失を生むこともあります。だからこそ、感情を扱う力、つまり「感情の統合力」は、戦略的なスキルなのです。
そして、その力を高めるためには「静寂の時間」が必要です。
静寂は、感情を翻訳する場所
ここで言う「静寂」とは、単に音のない空間ではありません。思考を止め、外の評価を切り離し、内側にある感情に耳を傾ける時間です。たとえば以下のような時間が、それにあたります。
・朝の数分、ノートに気持ちを書き出す
・帰宅後、ひと息ついてその日の違和感を見つめる
・週に一度、自分の内省をまとめる習慣をもつ
これらは一見、非効率に思えるかもしれません。ですが、未処理の感情が行動や判断に与える影響を考えると、実は「感情のクリアリング」は、最も効率的な戦略なのです。
自分のものか、誰かのものか」を見極める
感情の統合においてもう一つ重要なのは、「その感情は、自分のものか、他者や家系から影響を受けたものか?」という視点です。たとえば、
・「私はダメだ」と感じるとき、それは本当に自分の声でしょうか?
・子どもの頃に親から受け取った価値観を、いまだに信じていませんか?
・家族の中で「我慢強いことが美徳」とされていませんでしたか?
こうした問いかけを通じて、「自分に属さない感情」を見分けることができます。そして、その感情を「手放してもいい」と自分に許可することが、統合のプロセスにおいて非常に大きな一歩となります。
統合された感情は、「選べる人生」をもたらす
感情が統合されていないとき、私たちは「反応的」に生きています。けれど、統合が進むにつれて、「選択的」に生きられるようになります。
・本当にやりたいことにYesと言える
・自分を守るためでなく、信頼から行動できる
・誰かの期待ではなく、自分の感覚を信じられる
これが、「やすらぎの余韻」が人生にもたらす本当の意味です。感情に振り回されず、でも感情を否定することなく、ただ「あるがまま」で立っていられる状態。
ビジネスにおいても、プライベートにおいても、この静かな強さこそが、もっとも安定した「影響力」を生むのです。
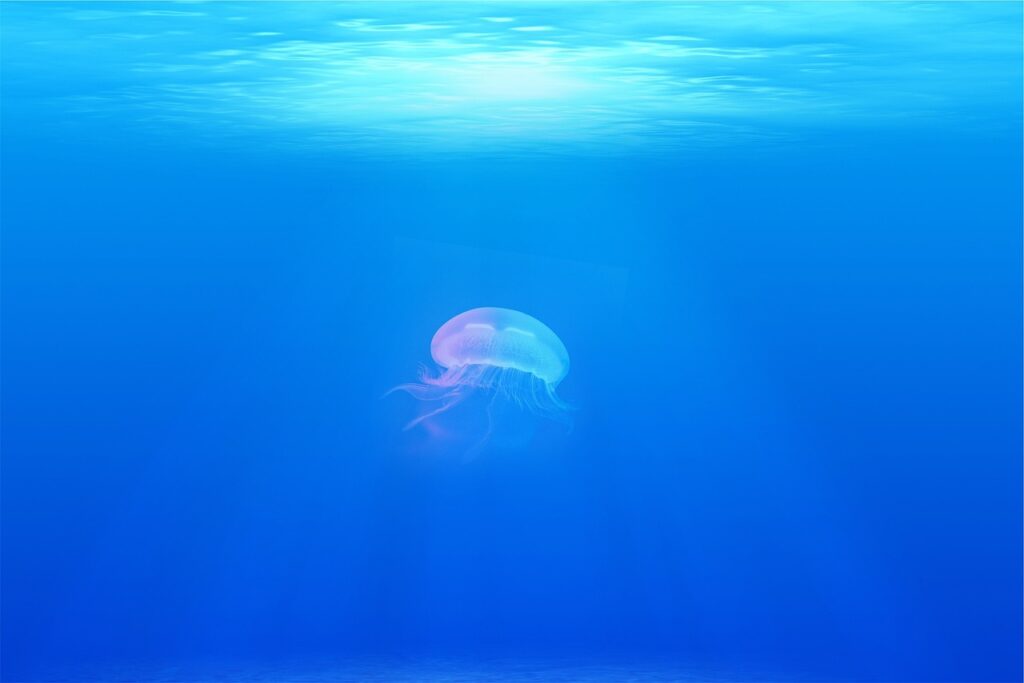
「やすらぎの余韻」が生まれる構造
「やすらぎ」は、偶然に生まれるものではありません。感情が整理され、心のノイズが静まったあとに、そっと訪れる「余韻」のようなものです。そのやすらぎを感じるためには、ある「構造」つまり、内面と外部環境の両方における「支え」が必要です。
ここからは、「やすらぎ」が自然に生まれてくるために必要な3つの要素について、丁寧に紐解いていきます。
1. 感情を言葉にできる「対話の場」
まず欠かせないのが、「感情を安全に表現できる場」です。それは、アドバイスや解決を求められる会話ではなく、「ただ話してもいい」と思える関係性のことです。
・話しているうちに、自分の本音に気づく
・相手が反応せず、受け止めてくれるから安心できる
・「わかろうとする姿勢」があるから、心がひらける
こうした体験は、感情を安心して「放電」できる環境をつくります。やすらぎは、感情を外に出すことで初めて生まれる「余白」に宿るのです。
2.評価から解放される「空間の静けさ」
次に重要なのが、「誰にも評価されない時間と場所」を持つことです。たとえば、
・スマホや通知をオフにして過ごすひととき
・誰かの期待や視線がない、ひとりの空間
・結果や意味を求めない、何も「しない」時間
現代は常に「意味」や「成果」が求められる社会です。その中で、「ただ静かにある」ことが、むしろ最も困難になっています。でも、感情の整理には、この「意味のない時間」こそが必要なのです。
それは、身体と心を「反応」から「休息」へと切り替える、回復の時間だからです。
3. 無条件に許される「承認の経験」
やすらぎの根本には、「どんな自分でも受け入れてもらえた」という経験があります。たとえば、
・話せなかった過去を、ただ静かに聞いてもらえた
・泣いても、怒っても、「そうだったんだね」と言ってもらえた
・何もしていないのに「いてくれるだけでいい」と言われた
こうした承認は、「がんばらないと価値がない」という刷り込みを緩めてくれます。それにより、安心して「本来の自分」に立ち返ることができるのです。これは家族やパートナーとの関係だけでなく、職場やチームの中でも同様です。「安心してそこにいていい」と思える空気は、組織の中に「やすらぎの文化」を根づかせる土台になります。
やすらぎは「戻ってこられる場所」でもある
これら3つの要素(対話・空間・承認)は、どれも一過性のものではありません。やすらぎとは、「戻ってこられる場」でもあるのです。
・外では戦っても、家ではほっとできる
・忙しい日々のなかでも、ふと立ち止まれる
・揺れても戻ってこられる「基礎の静けさ」がある
この「やすらぎの土台」があると、人はより大きな挑戦や変化に向かっていけます。なぜなら、心のどこかで「戻る場所がある」と知っているからです。そしてそれは、過去の痛みを消し去ることではなく、「大切に抱えてきた感情」とともに生きる力でもあります。
やすらぎの余韻を「習慣化する」
やすらぎは、特別な時間ではなく、日常の中で育てていくものです。
・安心して話せる人との時間
・評価から解放される空間の確保
・無条件に許される体験の記憶
これらが少しずつ積み重なることで、心のなかに「余韻としての静けさ」が定着していきます。
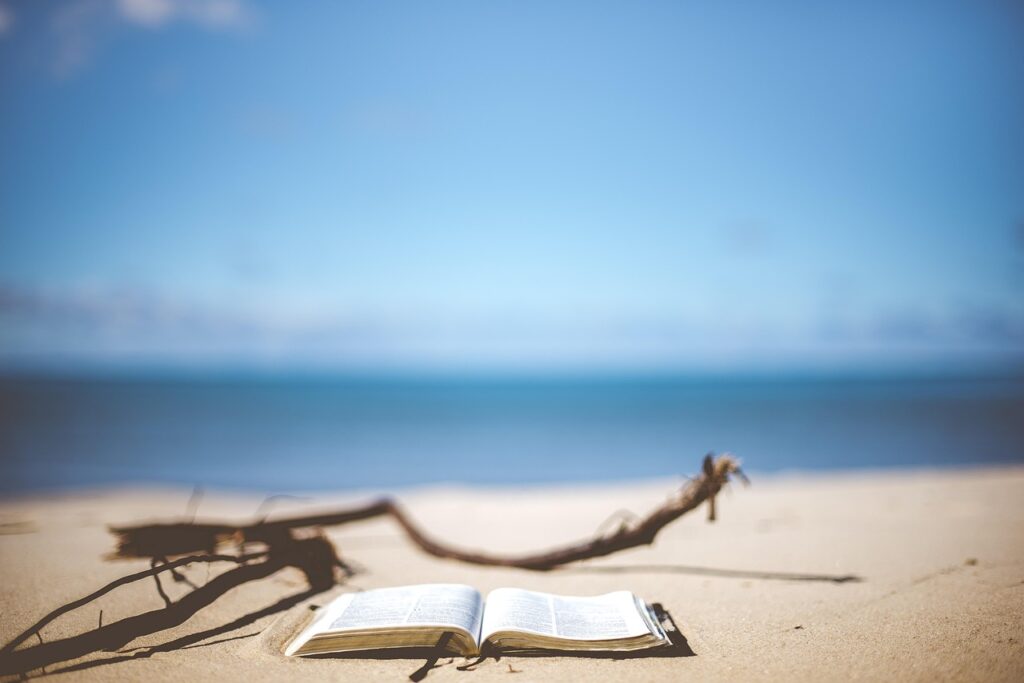
「やすらぎの余韻を見つける3つのステップ」
このワークは、あなたにとっての「やすらぎの構造」を見つけるための、内省的な問いかけです。1人でも行えますし、信頼できる相手との対話でも効果があります。
Step 1「やすらげた瞬間」を思い出す
次の問いに、できるだけ静かな気持ちで答えてみましょう。思い出せる範囲で、具体的な状況を描写するのがおすすめです。
・最近、心から「安心した」「ふっと力が抜けた」瞬間はいつですか?どこで?誰と?どんな気持ちでしたか?
Step 2 そのときの「構造」を書き出す
やすらげた瞬間には、必ず背景に「支えの構造」が存在しています。以下の問いに答えることで、自分にとっての「やすらぎの条件」が見えてきます。
・そのとき、どんな空気や環境でしたか?
(例:静かだった/誰も急かさなかった/無言でも安心できた)
・自分は、どんな自分でいられましたか?
(例:役に立とうとしなくてよかった/気をつかわずに笑えた)
・ 周囲の人は、どんなふうに接してくれましたか?
(例:話をさえぎらなかった/リアクションを反映したまなざしだった)
Step 3「今つくれるやすらぎ」を考えてみる
最後に、自分の生活の中で「それに近い構造を再現できる場面」を探してみましょう。
・ 週に1回でも、やすらげる時間をどこにつくれそうですか?
・誰と過ごすと、その感覚に近づけそうですか?
・今の自分が、もう少し安心できるように変えられそうなことは?
(補足) チームや家族で使う場合
このワークは、チームビルディングやパートナーシップでも効果的です。共有できる場合は、互いの「やすらぎの構造」を理解し合うことで、信頼関係が深まります。
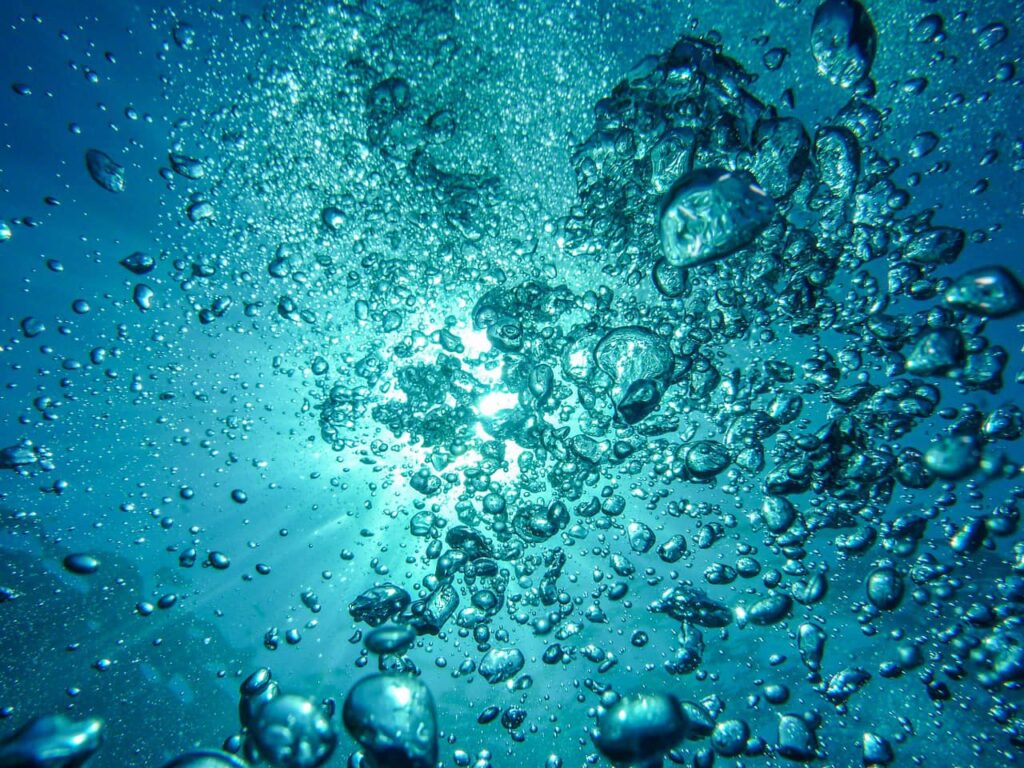
感受性と豊かさの「受け取り設計」
やすらぎは、感情の整理から生まれる「余白」です。そしてその余白には、次の可能性が自然と入り込んできます。そのひとつが、「豊かさを受け取る力」です。
人との関係、愛情、チャンス、報酬...私たちは日々、何かを受け取りながら生きています。でも実は、「受け取ること」には、意外なハードルがあるのです。
「受け取れない感受性」の正体
あなたはこんなことを感じたことはありませんか?
・褒められても「そんなことないです」と否定してしまう
・ありがとうを言われると、なぜか居心地が悪い
・ギフトを受け取ると、すぐに「何かお返ししなきゃ」と思う
これらの反応の裏にあるのは、「受け取ることへのブロック」です。そして、その多くが幼少期の体験や家族文化、さらには家系的な感情の継承から来ています。
・「遠慮が美徳」だった家
・「親のためにがんばる子」が愛された環境
・「もらうより与える」ことを求められた風土
こうした背景のなかで育った感受性は、やがて「自分は受け取ってはいけない」という信念をつくっていきます。
豊かさは「感じ取る力」に比例する
豊かさとは、実は「持っているかどうか」ではなく、「受け取れるかどうか」によって決まります。同じだけ愛されても、「それを感じられる人」と「受け取れない人」では、人生の質がまったく変わってくるのです。つまり、「感受性」とは「豊かさの受信機能」なのです。
・誰かの優しさを受け取る感性
・小さな喜びに気づける感性
・何気ない光景に心を動かされる感性
これらの感性が、「満たされている感覚」をつくります。そしてこの感受性は、静けさの中に育ちます。
外側の喧騒や評価から離れ、自分の内側と繋がることで、「今、ここ」にある豊かさに気づけるようになるのです。
感受性を「設計する」という視点
感受性や受け取り力は、生まれつきの才能ではありません。むしろ「日常の設計」によって、そして「継承された感情に気づくこと」によって、感受性を育てていくことができます。
たとえば、
・感じたことをメモに残す
・ありがとうをもらったら、黙って受け取る練習をする
・一日にひとつ、「今ここにある豊かさ」を数えてみる
こうした行為は、自分の「感受性の受信範囲」を広げていきます。そしてそれに比例して、心の中に「受け取り許可」が広がっていくのです。
これは単なる精神的な話ではありません。ビジネスにおいても、自己肯定感や報酬受容力、価格設定や契約交渉のような場面で、「受け取ることへの抵抗」があるかどうかは、直接的に成果に関わってきます。
自分に豊かさを許すということ
やすらぎの余韻は、自分に対する「静かな肯定」です。それは、「もうがんばらなくてもいい」と言われることではなく、「がんばってきた自分を、ここで一度抱きしめる」感覚です。何度も繰り返すことでその感覚が深まり、「受け取ること」に抵抗しなくなっていきます。それは褒め言葉に「ありがとう」と言えるようになることかもしれませんし、支援や好意を、罪悪感なく受け入れられるようになることかもしれません。
そうして、他人からだけでなく、「ご先祖」や「人生そのもの」からのギフトも、自然に受け取れるようになっていきます。
「受け取りの構造」を整えると、人生の流れが変わる
私たちは、「足りない」と感じることで行動を起こしがちです。でも本当は、「すでにあるものを受け取る力」が育つことで、人生の流れは大きく変わっていきます。「小さなことに気づく力」「自分に豊かさを許す力」「他人からの好意を、ありがとうと言える力」は、あなたの人生に新しい風を吹かせてくれるでしょう。

ご先祖とともに「今、ここ」を生きる感覚
「ご先祖」という言葉に、あなたはどんなイメージを持っていますか?
古い仏壇、白黒写真、静かな墓地...あるいは、漠然とした「過去にいた人たち」という距離感かもしれません。
でも本当は、ご先祖とは「過去の存在」ではありません。彼らは「今この瞬間」も、私たちの内側に静かに息づいています。
祈りとは「関係性を結び直す」行為
一般的に「祈る」とは、願いを届けたり、感謝を伝えたりする行為だと捉えられます。けれど、DESTINYの「ご先祖セラピー」における祈りとは、「記憶とつながりを再構築する」時間です。
・ ありがとうと言えなかった想いに、そっと触れる
・名も知らぬ祖先に「よく生きてくれた」と心を向ける
・苦しかった歴史の中にも「その選択を否定しない」と許しを込める
そういった祈りは、過去を浄化するのではなく、「過去」をありのまま受け止めることで、今の自分に安心を「取り戻す」行為なのです。
ご先祖は、過去に属していない
ご先祖は「昔の人」ではありません。彼らの記憶は、感情は、選択の記録は、今を生きる私たちの中に、そのまま流れています。
たとえば、
• 人間関係の癖に、祖父母と似た反応が出る
• 子育てのスタイルに、親からの言葉が反射的に出てくる
• 自分の人生のテーマが、先祖代々と共通している
これらは、ご先祖が「見えないレイヤー」として今も影響を与えている証です。だからこそ、「今、ここ」を整えることは、「過去と未来の流れをも整えること」につながっているのです。
継承とは、「繰り返す」ことではなく「選び直す」こと
私たちはよく「親のようにはなりたくない」と言いながら、無意識に同じ道を歩いてしまったりします。これは、「継承」の一面です。けれど、それがすべてではありません。
継承とは、「ただ繰り返すこと」ではなく、「そこから選び直す自由」を受け取ることでもあるのです。
• 祖母ができなかったことを、自分が形にしてみる
• 父の恐れを超えて、自分は信頼を選んでみる
• 代々の沈黙に代わって、想いを言葉にしてみる
この「選び直し」は、あなたの人生の物語であると同時に、ご先祖たちの物語の続きでもあるのです。
今を生きることが、ご先祖の供養になる
過去に何があったとしても、その流れのなかで「今、ここに生きている」あなたがいます。だからこそ、あなたが自分を生きること、悩みながらも選び直すこと、小さな幸せを受け取ること。それらすべてが、ご先祖にとって「最大の供養」になるのです。
彼らは、「祀ってほしい」「思い出してほしい」という願う以上に、「あなたに幸せでいてほしい」と願っているのかもしれません。
祈りとは、「いまを生きるための技術」でもある
静かに手を合わせる時間、日記の片隅に綴る感謝の言葉、夢のなかで出会った誰かの面影。
それらはすべて、「祈り」のかたちです。祈りとは、見えない誰かに何かを願うことではなく、「いまを丁寧に生きよう」と自分に戻ってくる技術なのです。
記憶は終わらない。つながりは、更新されていく。
ご先祖との関係性は、いまも続いています。祈るたび、感謝するたび、受け取るたび、そのつながりは、静かに更新されていきます。
「ご先祖セラピー」とは、過去を振り返るためのものではなく、「今、ここ」という時間を深く生きるための視点です。そしてあなたが、その視点を受け取り、選び、表現していくことこそが、次の世代にとっての「祈りの記憶」になっていくのです。

編集後記
長い文章を、ここまで読んでくださって本当にありがとうございます。
「ご先祖」と聞くと、どこか遠い存在に思えるかもしれません。けれど、私たちはその「遠さ」を越えて、日々のふとした瞬間に、「確かに何かとつながっている」そんな感覚を持ったことが、きっと誰しも一度はあるのではないでしょうか。
「なぜか涙がこぼれる夜」であったり、「うまくいかないことが、同じように繰り返される日々」や「本当は望んでいないのに、何度も選んでしまう関係や場所」
それらは「ただの偶然」ではなく、記憶や感情、そしてまだ名前のついていない「想い」の継承かもしれません。
私たちは、自分という存在だけで生きているのではなく、「いくつもの命の記憶」をまとってこの世界を歩いています。そのなかには、まだ癒されていない痛みも、誰かが願ったけれど叶わなかった夢も、きっと含まれていることでしょう。
でもだからこそ、今ここに生きている私たちが、自分の選択で未来を編み直すことには、とても大きな意味があります。
このお手紙を通して、もしもあなたが、少しでも「自分を見つめる時間」を持てたなら。
ご先祖という言葉に、ちょっとだけ親しみを持てたなら。
そして、「私は、このままでよかったんだ」と思えたなら。
それはきっと、どこかの誰かの祈りに応える瞬間だったのだと思います。
そしてなにより、あなた自身が「あなたを生き始めた」ということ。すべての言葉たちに目を通して、静かに心を寄り添ってくださったあなたへ、心から「ありがとう」を込めて。
また、このテーマにまつわる実践編やワーク、ご先祖セラピーのオンライン講座、PDFブックなども順次公開予定です。感想やご質問なども、ぜひお気軽にお寄せくださいね。この記憶の旅が、あなたのこれからにとって、やさしい風となりますように。
ご先祖セラピーに触れて「もう少し軽やかに知りたい」「日常の中で思い出していたい」と思ったら、ぜひ!こちらにも触れてみてください。
▼ Instagramでは、5匹のネコたちがやさしく語りかける「今日のひとこと」を毎日お届けしています。
▼ noteでは、感情の継承や家系の気づきについて、物語やエッセイの形で深掘りしています。
▼ アメブロでは、暮らしの中での気づきや、セラピーをもっと身近に感じられる日々の記録を綴っています。
それぞれの場所で、少しずつちがう「視点から、お伝えしています。
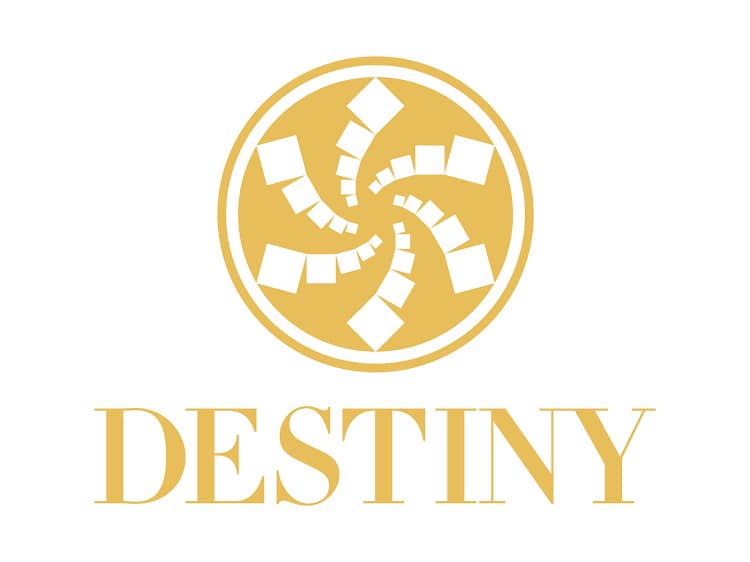
あなたとあなたの大切な人の人生が愛で満ち溢れるものであり続けますようにとの願いを込めてDESTINYからのお手紙をお届けさせていただいています。
「このテーマについて知りたい」
「こんなサービスがあったらいいな」
「今、こんなことで悩んでいます」
あなたの声をぜひ聴かせていただけませんか?
https://docs.google.com/forms/d/1cmI3soV5IdmhqFvLVkQw0pNYEtJqS07syR2NuVXk0xk/edit